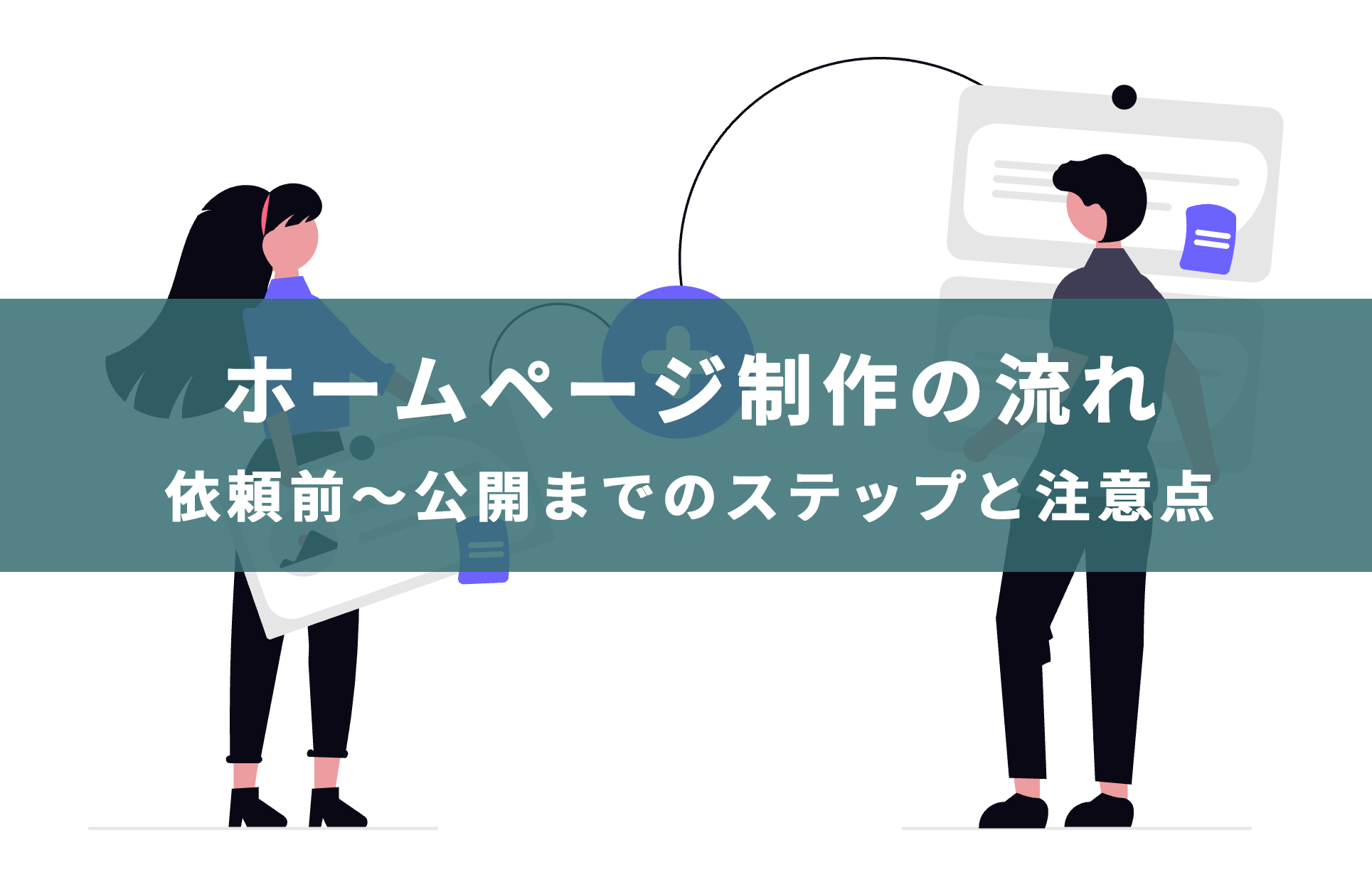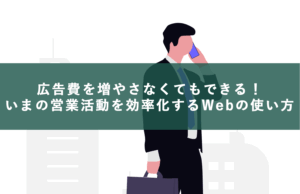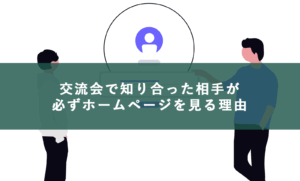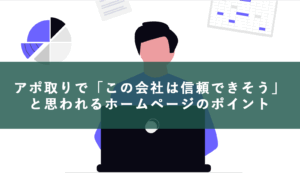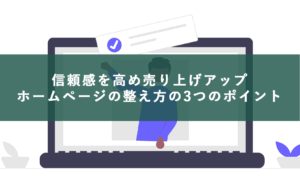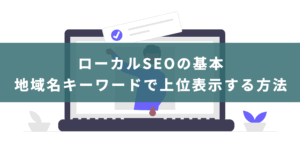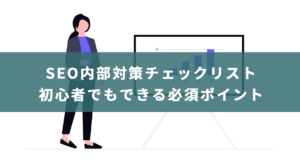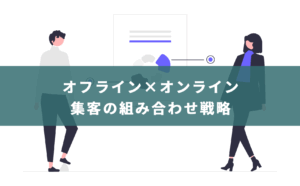こんな方におすすめの記事です
- 制作の流れを短時間で正しく把握したい
- 見積や納期の現実的な目安を知りたい
- 依頼前に何を準備すべきか具体的に知りたい
- 社内の承認や稟議をスムーズに進めたい
- 制作会社の選び方と比較軸を整理したい
- 初めてでも失敗しない進め方を学びたい
- 公開後に何を測り改善するか理解したい
この記事でわかること
- 依頼前から公開後までの全体像が分かる
- 一般的な制作期間と遅延の要因が分かる
- 社内外の関係者と決める事項が分かる
- 目的設定とターゲット定義の型が分かる
- 見積比較と契約確認の要点が分かる
- 原稿・写真の準備と権利の基本が分かる
- 公開後の計測と改善の流れが分かる
はじめに
制作の全体像を把握するメリット
全体像が分かると、いつ何を決めるかが明確になり、迷いが減ります。先に目的と優先順位を決めれば、見積やスケジュールの話が具体的に進み、やり直しも少なくなります。誰が担当し、どこで承認するかを決めておくと、社内調整が早まり、余計な費用や待ち時間を抑えられます。
「中小企業のWebマーケティング|戦略ロードマップ」
無料ダウンロード資料配布中
【こんな方におすすめ】
- Webからの集客を増やしたいが、どの施策が効果的かわからない
- ホームページやSNSを活用しているが、問い合わせや売上につながらない
- 少ない予算・人員でも実践できるWebマーケティングの方法を知りたい
【この資料でわかること】
- 中小企業が成果を出すためのWebマーケティングの基本と成功ステップ
- 「アクセスが増えない」 「問い合わせが少ない」など、よくある課題の解決策
- 限られたリソースでも実践できる、最新のデジタルマーケティング手法
ホームページ制作の全体の流れ
制作期間の目安を押さえる(一般的に1〜3か月)
一般的な企業サイトなら、依頼から公開まで1〜3か月が目安です。ページ数が多い、写真撮影が必要、特殊な機能がある場合は長くなります。実は社内承認の速度も大きな要因です。最初に大まかな日程と承認日を決め、遅れた場合の代替案も用意しておくと、計画が安定します。
主な関係者と役割を理解する(社内と制作側の担当)
社内は「決裁者」「窓口担当」「情報提供者(営業・現場)」が中心。制作側は「ディレクター(進行)」「デザイナー」「エンジニア」「ライター(任意)」です。誰が何を決めるか、連絡窓口は誰かを先に決めましょう。不在時の代行者も決めておくと、止まらずに進められます。
工程のつながりを俯瞰する(企画→設計→制作→公開→運用)
流れは「企画→設計→デザイン→実装→テスト→公開→運用」の順です。前工程の決定が後工程の土台になるため、早い段階で目的・構成・素材を固めるほどスムーズです。原稿や写真が遅れると全体が止まります。各工程の“入口条件(必要物)”と“出口成果物(決まったこと)”を明確にしましょう。
ステップ1|依頼前の準備(企画・目的設定)
目的を具体化して優先度を決める(例:月◯件の問い合わせ)
「問い合わせを月◯件」「資料請求を月◯件」など、数で目標を置きます。最優先を一つに絞ると、言葉と導線がブレません。目的から必要ページやボタン配置が決まり、判断が速くなります。数字があると制作会社との会話も具体化し、費用対効果を後で評価しやすくなります。
ターゲット像を一文で言語化する(誰に読んでほしいか)
例:「地元で改装業者を探す店舗オーナー。予算と納期が不安」。この一文で、見出し・写真・事例の選び方が決まります。相手の悩みと決め手、よく使う言葉もメモしましょう。みんなで同じ前提を共有できると、社内の合意が早まり、制作物の方向性もぶれにくくなります。
競合サイトを比較して差別化する(強みを3つに絞る)
競合を3社選び、「訴求の分かりやすさ」「事例の充実度」「問い合わせのしやすさ」を観察します。自社が勝てる点を3つに絞り、数字や実例で裏付けましょう。強みが多すぎると印象が弱まります。選ばれる理由を短く言い切れる状態まで削っておくと、制作全体が整理されます。
必要ページと機能を先に棚卸し(必須/あとで追加)
基本は「トップ・サービス・事例・会社情報・FAQ・問い合わせ」。必要なら「料金」「採用」を追加します。機能は「問い合わせフォーム」「資料ダウンロード」「検索」「多言語」など。まず“必須”と“あとで追加”を分けておくと、見積比較がしやすく、段階導入もしやすくなります。
ステップ2|制作会社の選定と見積もり
選定の判断基準をそろえる(価格だけで決めない)
価格だけで選ぶと失敗します。「品質(同業の実績)」「速度(体制と承認SLA)」「保守(公開後の対応)」「相性(説明の分かりやすさ)」で評価しましょう。軸ごとに点数化し、根拠をメモします。主観を減らせば、社内の納得感が高まり、決定も早くなります。
見積比較は内訳で判断する(ページ数・修正回数など)
ページ数、個別デザイン数、原稿・写真の分担、スマホ対応・速度・計測の範囲、テスト対象、修正回数を同条件で比較します。条件が違うと公平に比べられません。曖昧な点は質問で確定し、表に転記。追加費の発生条件(変更時の単価)も必ず確認しましょう。
契約形態と支払い条件を整える(検収基準と所有権)
契約は「請負(成果で検収)」「準委任(工数で精算)」「サブスク(月額)」が代表です。支払い回数と割合、検収の基準、遅延時の取り決めを明確に。デザイン・コード・写真の所有権やデータの受け渡し方法も重要です。不明点は文書で合意し、後のトラブルを防ぎます。
ステップ3|要件定義・構成設計
サイトマップで全体骨子を可視化(ページの並びと役割)
全ページの並びと役割を図にして、重要度を設定します。近い内容は統合し、回遊が自然になる順番へ並べ替えましょう。ここで“抜け”に気づければ、後工程の手戻りが減ります。まず骨子を固めることが、納期と費用を守る最短ルートです。
ワイヤーで画面の役割を決める(何を上に置くか)
ワイヤーフレームはページの設計図です。見出し、本文、写真、ボタンの位置を簡単な箱で示し、スマホの一画面で何を伝えるかを最優先に決めます。重要情報を上に置き、迷わない導線を作りましょう。ワイヤーで合意してからデザインへ進むと、迷いが少なくなります。
原稿と素材を前倒しで準備する(文章・写真・許諾)
原稿と写真が遅れると、デザインも実装も止まります。テンプレに沿って先に文章を埋め、撮影は用途・構図・点数を指示書にまとめます。写真の権利や掲載許可も同時に確認。素材が早くそろうほど、全体工程が滑らかに進み、品質も安定します。
ステップ4|デザイン制作
トップ案で方向性を固定する(色・写真・訴求の順番)
最初にトップページの案で、色・写真・文字サイズ・訴求の順番を決めます。ここで「誰に何を伝え、次に何をしてほしいか」を合わせましょう。方向性が固まれば、下層への展開がスムーズです。修正は回数と期限を決め、長期化を防ぐのがコツです。
下層へパターンを展開する(一貫した部品・見た目)
見出し、ボタン、表、FAQなど、よく使う部品をパターン化します。同じルールで作ると見た目がそろい、更新もしやすくなります。ページごとに個性を出しすぎず、使いやすさを優先しましょう。写真のトーンも合わせると、全体の信頼感が高まります。
色・フォント・写真を最適化(読みやすさ最優先)
色はブランドカラーを軸に、文字が読みやすい明暗差を確保。フォントはサイズと行間を広めに設定し、スマホでも楽に読めるようにします。写真は明るさ・構図をそろえ、重さは軽く最適化。見た目の統一と読みやすさが、成果につながります。
ステップ5|コーディング・システム開発
HTML/CSSで土台を正しく作る(表示速度と基本品質)
HTMLは情報の骨組み、CSSは見た目のルールです。正しい骨組みで作ると、検索にもユーザーにも優しくなります。画像を軽くし、不要な読み込みを減らして速度を確保。土台がしっかりしているほど、後の修正が楽になり、長期の運用コストも抑えられます。
CMSを使い更新しやすくする(社内でニュース更新)
CMS(更新を簡単にする仕組み)を導入すると、ニュースや事例を社内で追加できます。入力項目は多すぎない方が運用しやすく、承認フローと権限も決めておくと安心です。簡単なマニュアルを用意し、更新が続く体制を作ることが、成果につながります。
全デバイスで快適に表示する(スマホ・PCの最適化)
スマホ、タブレット、PCで文字や画像の見え方を調整し、ボタンは指で押しやすい大きさに。画像は軽く最適化し、読み込みを速くします。どの画面でも「次にしてほしい行動」が分かるよう、ボタン位置と導線を工夫しましょう。使いやすさが成果を左右します。
ステップ6|テスト・修正
表示崩れとリンクを総点検(主要端末・主要ブラウザ)
iPhone・Android・PC、Chrome・Safari・Edgeなどで、文字の折り返し、画像の切れ、配置の崩れを確認。リンク先が正しいか、戻る動作が自然かもチェックします。小さな不具合の積み重ねが印象を下げます。公開前に丁寧に潰しましょう。
フォームと決済を厳密に検証(送信〜自動返信まで)
問い合わせや注文フォームは、入力→送信→自動返信まで通しで試験します。必須項目のエラー表示、電話・メールの入力補助も確認。決済がある場合はテスト環境で金額や流れを実機検証します。ここは成果に直結するため、複数人でチェックしましょう。
マルチ環境で最終チェック(4G/5G回線や404確認)
Wi-Fiだけでなく4G/5Gでも表示速度を確認。誤ったURL時に404ページが正しく表示されるか、旧URLからの転送、サイトマップ送信の準備も点検します。問題点は一覧化し、期限と担当を決めて迅速に修正しましょう。
ステップ7|公開
本番サーバーへ安全に反映(バックアップと手順書)
公開前にバックアップを取り、反映手順を文書化します。公開後はトップ、サービス、問い合わせなど主要ページを再確認。計測タグが動作しているか、エラーが出ていないかもチェック。万一の連絡先と対応手順を共有しておくと、初動を素早くできます。
ドメインとSSLを正しく設定(www統一・転送・地図)
ドメインを本番に向け、SSL(暗号化)を設定。wwwあり/なしを統一し、旧URLから新URLへ転送します。会社情報ページの地図や連絡先の表示も再確認。設定が正しいと安心感が高まり、検索の評価も安定します。
公開後の初動を最適化(監視・サイトマップ送信)
公開直後1〜2週間は、毎日軽い点検を行います。アクセス数、問い合わせ、エラー有無を確認し、検索エンジンにサイトマップを送信。SNSや顧客向けに公開告知を行い、初動の訪問を増やします。気づいた不具合は小さいうちに素早く直しましょう。
ステップ8|運用・改善
データで課題と機会を発見する(アクセスと問い合わせ)
毎月「アクセス数」「問い合わせ数」「電話タップ数」などを確認。どのページが成果に貢献しているか、どこで離脱が多いかを把握します。数字が見えると、次に直す場所が自然と決まります。小さな改善を続けることが、長期の成果につながります。
更新とSEOで資産を育てる(見出し・内部リンク改善)
新しい事例やお知らせを定期的に追加し、見出しを分かりやすく更新。関連ページへ内部リンクを張り、回遊を促します。画像は軽く、代替テキストも整えましょう。検索に強くなると、広告に頼りすぎず集客できます。継続が一番の近道です。
守りの運用で安心を担保する(バックアップと権限管理)
定期バックアップ、ソフトの更新、権限の見直しを行います。退職者のアカウント停止やパスワード変更も忘れずに。緊急連絡先と復旧手順を文書化しておくと、万一の時に被害を最小限にできます。安心して運用できる環境が、攻めの改善を支えます。
まとめ
成功の鍵は「目的を一つに決める」「素材を前倒しで揃える」「同じ条件で見積を比べる」の三点です。工程ごとに入口条件と出口成果物を明確にし、承認の期日を早めに決めれば、1〜3か月でも十分に公開できます。まずは自社の目的とターゲットを一文で固め、必要ページの棚卸しから始めましょう。
無料相談のご案内
制作やリニューアルで迷ったら、専門家に相談するのが近道です。ご要望やご予算、納期に合わせて最適な進め方をご提案します。はじめての方にもわかりやすい説明を心がけ、公開後の運用や集客まで一貫してサポート可能です。まずは気軽にお声がけください。
- 現状ヒアリングと課題の可視化
- 目的別の進め方と概算費用提示
- スケジュール案と体制のご提案
- 公開後サポートと改善方針の共有
- 他社見積との比較観点アドバイス
人気の関連資料のご案内
準備をスムーズに進められるよう、無料のチェックリストやテンプレートをご用意しています。制作前の要件定義シート、原稿作成の見出しテンプレ、SEOの基本チェックなど、すぐに実務で使える内容です。ダウンロードして社内共有し、共通認識づくりにお役立てください。
- 中小企業のウェブマーケティングロードマップ
- 今のホームページで大丈夫?ホームページ診断チェックリスト
- 採用×ホームページ|自社にあった人材を採用するためのコンテンツ戦略ガイド
- 基礎からわかるWebマーケティング入門ガイド
ホームページのサブスクという選択肢も
最近ではホームページのサブスクサービスも出てきており、高いデザイン性やクオリティのサイトがコストを押さえて運用することができるようになりました。
ウィルサポは月額9,800円からオリジナルのホームページをもてるサブスクサービスです。
SEO面もしっかりと対策した上で、お客様のビジネスの成長をサポートさせていただきます。LP制作や新規サイトはもちろん、サイトのリニューアルにも対応しております。
- 初期費用なしで月額9,800円から
- フルオーダーでデザイン作成
- サーバー、ドメイン費用無料
- サイトの保守費用無料
- 契約期間の縛りなし
- 集客サポートプランあり