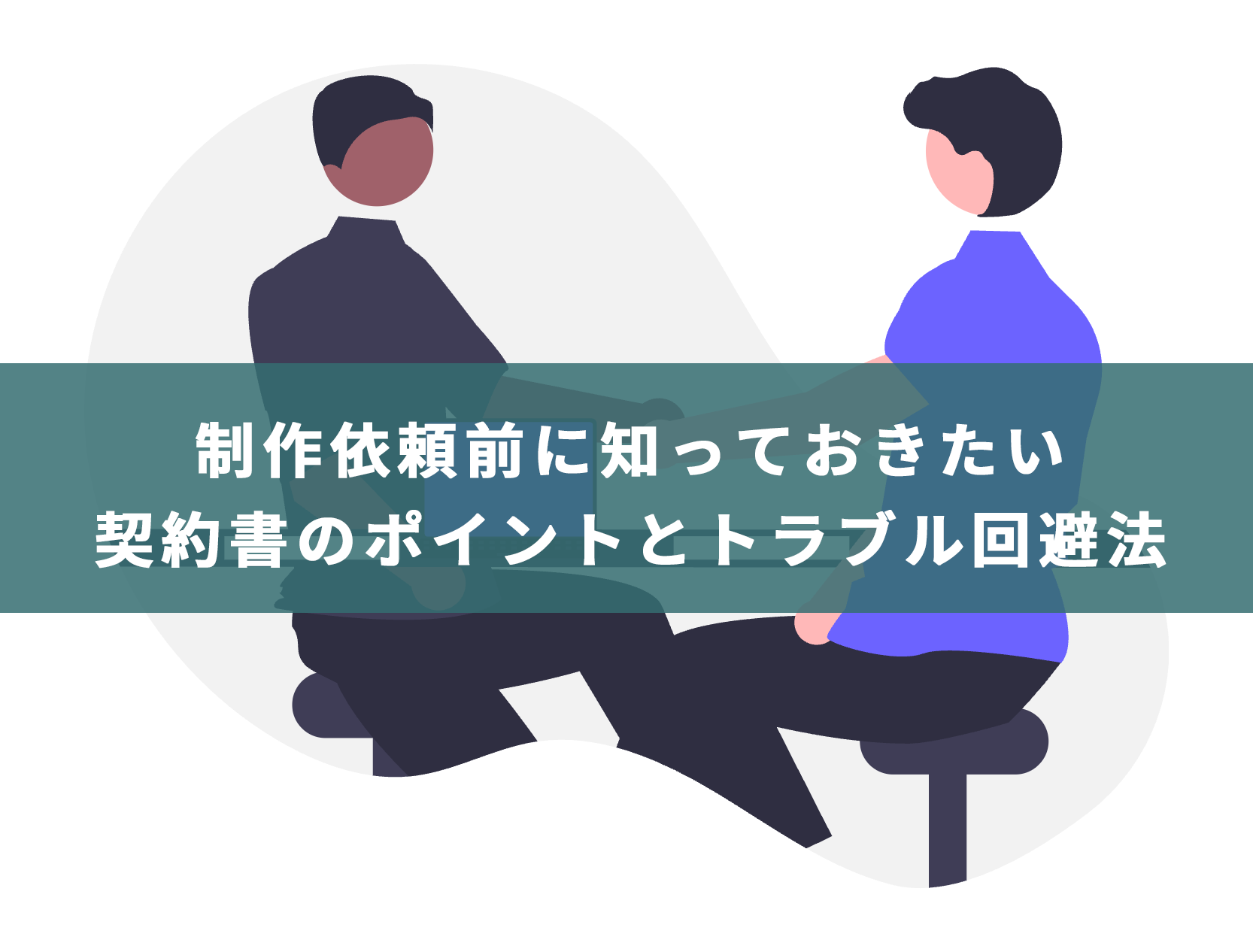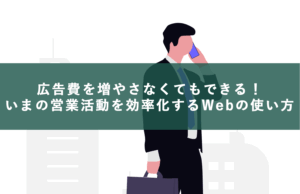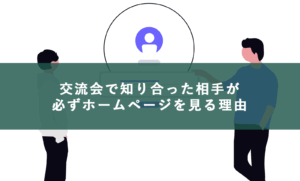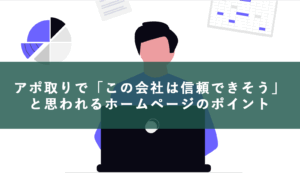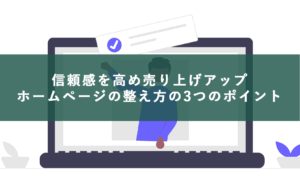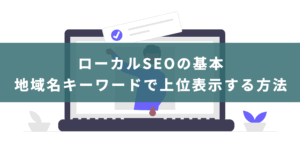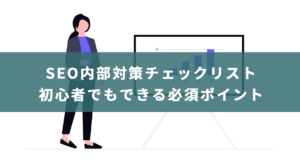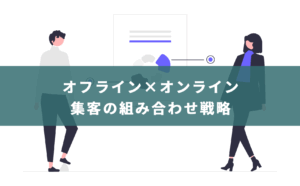こんな方におすすめの記事です
- 発注前に契約の要点だけ押さえたい
- 追加費用や納期遅れを避けたい
- 成果物の所有権を明確にしたい
- 検収や保証の線引きを決めたい
- 保守・運用の範囲を整理したい
- 秘密情報と個人情報を守りたい
- 赤旗サインを見抜けるようにしたい
この記事でわかること
- 契約方式ごとの違いと選び方
- 作業範囲と成果物の定義方法
- 料金・支払い・追加費の決め方
- 変更管理と遅延時の対処手順
- 権利・利用許諾の基本ルール
- 品質・セキュリティの基準づくり
- 署名前の最終チェック手順
はじめに(この記事のゴール)
契約で守れること/避けられるミス
契約書は「誰が・いつまでに・どこまで・いくらで」行うかを言葉で固定する道具です。先に決めておけば、追加費や納期の食い違い、所有権の誤解、品質の期待差を防げます。本記事は、最低限入れておく条項と確認手順を整理。読むだけで、よくある揉め事の大半を避けられる状態を目指します。
読み方(上から/気になる所だけ)
時間があれば上から順に。急ぐなら「作業範囲」「料金」「権利」「検収」「保守」の章だけ拾い読みしてください。各見出しは1テーマ1ポイントで完結。最後の「赤旗サイン」と「署名前チェック」に沿って確認すると、抜けが自然に埋まります。必要箇所を印刷し、社内共有すると効果的です。
「中小企業のWebマーケティング|戦略ロードマップ」
無料ダウンロード資料配布中
【こんな方におすすめ】
- Webからの集客を増やしたいが、どの施策が効果的かわからない
- ホームページやSNSを活用しているが、問い合わせや売上につながらない
- 少ない予算・人員でも実践できるWebマーケティングの方法を知りたい
【この資料でわかること】
- 中小企業が成果を出すためのWebマーケティングの基本と成功ステップ
- 「アクセスが増えない」 「問い合わせが少ない」など、よくある課題の解決策
- 限られたリソースでも実践できる、最新のデジタルマーケティング手法
契約の基本(まず押さえること)
契約方式の違い(請負・準委任・サブスク)
請負は「完成」を約束し、検収で成果物を受け取る契約。準委任は「作業そのもの」を提供し、完成は保証しません。サブスクは月額で保守や小修正を続ける形です。どれを選ぶかで責任や支払いの考えが変わります。制作本体は請負、運用は月額など、併用も現実的な選択です。
当事者と窓口の役割(決裁者・担当・連絡)
契約書には法人名・住所・代表者を正確に記載。実務では、決裁者・窓口担当・技術担当の役割を分け、誰が何を承認するかを明記します。連絡手段はメールとチャットを併用し、議事録は必ず共有。承認の期限と代行者も最初に決めると、担当不在でもプロジェクトが止まりません。
作業範囲と成果物(スコープを明確に)
やること/やらないことの線引き
ページ数、対象機能、対応ブラウザ、対応端末、修正回数など、範囲を具体的に書き出します。逆に「やらないこと」も列挙し、例外を潰しておくのがコツ。後からの追加は「見積・合意・日程再設定」で受けるルールを契約に入れます。線引きが明確だと、余計な衝突が減ります。
成果物の定義(データ・ソース・納品形態)
納品ファイルの種類(HTML/CSS/JS/画像)、CMSのデータ、設計資料、編集権限の付与など、形と範囲を定義します。ソースコードの提供有無、制作データ(PSD/AI等)の扱い、クラウド納品か物理媒体かも明確に。引き渡し後に編集できる状態をどこまで保証するかも決めましょう。
受け入れ基準と検収手続き
「表示崩れがない」「フォーム送信が成功する」など、検収基準を数値や条件で書きます。検収期間(例:7日)を設定し、指摘がなければ自動検収とする条項も有効。指摘が出た場合の修正期限や再検収の流れも記載。合格ラインを先に決めると、主観のズレを小さくできます。
料金と支払い(お金のルール)
見積内訳の見方(ページ数・機能・修正回数)
金額は「設計・デザイン・実装・テスト・PM」で分解し、ページ単価や機能単価、修正回数の前提を確認します。撮影・原稿・素材費は別計上が一般的。内訳を比べれば、安い理由や高い理由が見えます。比較は合計額でなく、同じ条件に揃えた上で行いましょう。
支払い条件(着手・中間・検収の比率)
一般的には着手金・中間金・検収金の三分割。割合は30-40-30などが目安です。支払期日、請求書発行のタイミング、遅延時の利息、通貨と振込手数料の負担先も明記。着手金は作業開始の合図、中間金は主要成果の提出と連動させると、進捗とキャッシュが安定します。
追加費用の発生条件と単価
要件追加、修正回数超過、写真追加、急ぎ対応など、発生条件と時間単価・機能単価を先に決めます。軽微修正の定義(例:文言差し替え)と大幅修正の定義(例:レイアウト変更)も分けて記載。合意なしの無償対応が常態化しないよう、手順と費用のルールを見える化します。
スケジュールと変更管理
里程標と承認者/期限の設定
「構成確定→トップデザイン→下層パターン→実装→テスト→公開」の節を作り、各節で承認者と期限を決めます。承認遅れが出た場合の影響も明記。ガントチャートや週次の定例で可視化すれば、早めに修正が効きます。節目ごとに成果物を残し、次工程の入口を守りましょう。
変更要求の手順と合意書の作り方
変更は「要望→影響(費用/納期/品質)→見積→合意→実施」の順で運用します。口頭合意は誤解のもと。変更管理表に履歴を残し、双方が署名した合意書(メール合意でも可)で固定。小さな変更も積もれば大きな影響になります。手順を決め、例外を作らないことが重要です。
遅延時の対応(予備日・代替案・優先順位)
工程ごとに予備日を設定し、遅れが出たら優先度の低い作業を後回しに。公開日が固定なら、ページを分割して段階公開も選択肢。外部依存(撮影・翻訳)は前倒しにしてリスクを下げます。遅延報告は早いほど対策の幅が広がるため、即時共有のルールを契約に入れておきます。
権利と利用許諾(知的財産の取り扱い)
ソースコード・デザイン・写真の所有権
誰が何を所有するかを分けて定めます。納品後のサイトデータとカスタムコードを譲渡、ベースとなるライブラリは利用許諾など、実態に合わせた条文に。写真は撮影者の著作権と被写体の肖像権の両面に注意。社内で改変できる範囲と、出典クレジットの要否も書いておきます。
フォント・素材・プラグインのライセンス
フォントや素材、CMSプラグインには各社の利用条件があります。商用可否、配布可否、サイト数制限、更新の必要性を確認。ライセンス費は誰が負担するか、契約終了後も使えるかを明記。将来の差し替え手順も決めておくと、更新や運用移管がスムーズになります。
再利用・改変・二次利用の可否
制作物の再利用(別案件での流用)、改変(色・レイアウト変更)、二次利用(広告・印刷物への展開)の可否を具体的に。許可する場合は範囲とクレジット表記の要否を明記。禁止するなら根拠を示し、代替手段を提示します。曖昧を残すと、後の広報物で衝突が起きやすくなります。
品質とセキュリティ(基準を数値で)
表示速度・スマホ対応・アクセシビリティ
速度は画像最適化やキャッシュで改善でき、スマホ表示はレスポンシブ対応が基本です。基準は「主要端末で表示崩れなし」「コントラスト比と文字サイズの目安」など、測れる形で。全ページ同水準を求めるのではなく、主要導線ページを優先して達成する考えが現実的です。
セキュリティ(SSL・更新・脆弱性対応)
常時SSL、CMSとプラグインの更新、管理画面の二段階認証、権限の最小化は必須項目です。脆弱性が見つかった場合の対応時間や連絡手順、バックアップの頻度も契約で明確に。万一の改ざん時は、まず停止・復旧・報告の順で進めることを、双方で確認しておきましょう。
バグ対応範囲と保証期間
公開後の不具合に対して、どこまで無償で直すか、期間は何日かを定めます。仕様変更に当たるものは有償、明らかなバグは無償など、線引きを例付きで記載。連絡から対応開始までの時間目安も決めておくと安心。保証が終わった後の保守契約への切り替えも提案しましょう。
保守・運用とSLA(公開後の約束)
サポート時間・窓口・応答時間(SLA)
受付時間(例:平日10〜18時)、窓口(メール/チャット/電話)、初回応答時間(例:4時間以内)を明記。緊急時の連絡網と、優先度の定義も合わせて決めます。問い合わせの記録方法や、定例報告の頻度を固定すると、対応の質が安定し、社内の共有もスムーズになります。
月額保守の範囲(軽微修正・監視・バックアップ)
月額に含む作業(更新、監視、バックアップ、軽微修正)と、含まない作業(新規機能、撮影、文章作成)を分けて記載。作業量の上限や、チケット制の本数など、運用の単位を決めます。上限を超えた場合の追加料金も明確に。予算の見通しが立ち、無理なく続けられます。
解約・引き継ぎ時のデータ返却
解約の予告期間、返却するデータの種類(サイトデータ、画像、設定)、形式(ZIP、CSV)、受け渡し方法を定義。移管作業の有償・無償も書きます。アカウントやドメインの所有者は依頼側に統一が基本。引き継ぎリストがあると、担当者が変わっても安全に移行できます。
秘密情報と個人情報
NDAの範囲・期間・違反時の扱い
秘密情報の定義(営業・技術・顧客情報等)、開示方法(書面・口頭)、有効期間、第三者提供の禁止を記載。違反時の対応(差止・損害賠償の範囲)も明確に。必要最小限の共有に留め、アクセス権を限定。終了後の返却・破棄の方法も、条文に落としておくと安心です。
個人情報・顧客データの取り扱い
問い合わせデータ等の扱いは、取得目的、保管方法、閲覧権限、委託先管理まで決めます。テスト用の個人情報はダミーを使用し、本番環境へのアクセスは限定。事故時の報告手順と期限も定め、ログを残す運用に。フォームの同意文とプライバシーポリシーもセットで整備します。
契約の終了とトラブル時
キャンセル・中止・違約金
発注後の中止は段階に応じて実費や成果に応じた精算が一般的。着手前・設計中・実装中など、区分ごとの費用割合を決めます。違約金や解除事由も双方対等に。やむを得ない事情(天災・長期停止等)への対応も条文化し、感情に頼らず淡々と処理できるように備えます。
納期遅延・品質不一致の対応手順
遅延時は、影響範囲と新しい工程表を提示し、優先順位を再調整。品質不一致は、契約の受入基準に照らして事実確認→是正期限→再検収の流れで処理。裁量ではなく、決めた手順で前に進めます。感情的な応酬を避けるため、窓口を一本化し、記録を残す運用が有効です。
紛争解決(窓口・調停・管轄)
まずは担当窓口で協議し、解決しない場合は第三者の調停へ。それでも難しければ、合意した管轄裁判所での解決とします。手順が決まっていれば、行き詰まりでも次の一手が選べます。エスカレーションの段階、通知方法、期限を契約に書き、落ち着いて進められる環境を作ります。
赤旗サインとチェックリスト
要件が曖昧/見積内訳が不明
要件がふわっとしたまま進むと、費用も納期もぶれます。見積に根拠がなく、工数や単価の説明ができない場合も要注意。まずは前提条件をそろえ、ページ数・機能・修正回数で内訳を出してもらうこと。比較は同条件で。説明が曖昧なら、契約前にクリアにしてからにしましょう。
- 要件を一枚で文書化して確認する
- ページ数と機能を数量で明記させる
- 修正回数と範囲を定義してもらう
- 単価と工数の根拠を質問で深掘る
- 別料金条件を箇条書きで提出させる
- 合計額ではなく内訳で比較検討する
所有権が不明/ソース非開示
誰が何を所有するか不明だと、更新や移管で揉めます。ソースや編集権限の提供がない契約も後々の足かせに。譲渡・利用許諾の範囲、データ返却の形式、アカウントの所有者を先に固定。納品後も社内で運用できるかを基準に、条文の抜けを埋めてから署名しましょう。
- ソース提供の有無と形式を明記する
- CMSの編集権限範囲を取り決める
- アカウント所有者を依頼側にする
- データ返却の手順と期限を定義する
- 二次利用の可否と表記を決めておく
口約束が多い/書面が整っていない
口頭合意は人によって記憶が変わり、後で食い違いの火種になります。決まったことは議事録に残し、変更は合意書で固定。SLAや検収基準など、数字で測れる項目は数値化。書面が弱い案件は、進行の見える化が不十分なことが多いです。迷ったら、紙に落とすを徹底しましょう。
- 会議後に議事録を即日共有する
- 決定事項は担当と期限を併記する
- 変更は必ず合意書に切り替える
- 数値基準で合格ラインを定義する
- 連絡手段と保管場所を統一する
署名前の最終確認
RFPと見積・契約の一致を確認
要件書(RFP)に書いた前提が、見積と契約に反映されているかを突き合わせます。範囲・納期・修正回数・検収基準・権利・保守の六点が一致していれば大きな事故は避けられます。行間で解釈が分かれそうな箇所は、言い換えて平易な文に。迷いはここで必ず解消します。
- ページ数と機能の数量が一致している
- 納期と里程標の期日が一致している
- 修正回数と定義が三文書で同一
- 検収基準が数値で揃って記載
- 権利・返却・編集権限が明文化
- 保守範囲とSLAが矛盾していない
合意事項の一枚サマリーを作る
プロジェクトの全体像をA4一枚に要約します。目的、範囲、納期、費用、合格基準、変更手順、連絡網を図と短文で整理。誰が見ても同じ理解になる資料があると、社内の決裁も早く、実務の迷いも減ります。印刷して打合せで確認、変更時は日付を入れて更新しましょう。
- 目的と成果のゴールを一行で記載
- 主要マイルストーンを横並びで整理
- 費用内訳と支払い時期を明記する
- 合格基準と検収手順を図解で示す
- 変更手順と担当窓口を掲載する
- 緊急時の連絡網を下部に固定
ひな形とメモ(活用テンプレ)
作業範囲テンプレ(例:必須・任意・除外)
範囲は「必須(今やる)」「任意(後でやる)」「除外(やらない)」の三段で管理すると明快です。各項目に数量と合格基準を付け、後から見ても判断できる形に。表計算でテンプレを作り、案件ごとにコピー。比較も早く、会議の決定も揺れません。まずは自社版を一つ作りましょう。
- 必須・任意・除外の三段で区分する
- 各項目に数量と期日を付ける
- 合格基準を短文で明記する
- 担当者と承認者を併記して固定
- 変更時は履歴列に追記する
変更管理表/議事録テンプレ
変更管理表は「依頼→影響→費用→納期→状態→合意日」。議事録は「決定事項・宿題・期限・担当」を上部に、本文は簡潔に。テンプレを先に配り、誰が書いても同じ型にします。履歴が整っていれば、記憶ではなく記録で進められ、トラブル時も落ち着いて対処できます。
- 変更票は一行一変更で管理する
- 影響は費用・納期・品質で分ける
- 合意日は必ず日付で固定する
- 議事録は翌日までに配布する
- 版番号と更新者を明記して保存
まとめ
契約で守るのは関係性ではなく「共通のルール」です。範囲・料金・権利・検収・保守を先に言葉で固定し、変更と遅延の手順を決めるだけで、ほとんどのトラブルは避けられます。今日やるべきは、前提条件の一枚化と赤旗チェック。準備が整えば、制作は静かに速く進みます。
無料相談のご案内
制作やリニューアルで迷ったら、専門家に相談するのが近道です。ご要望やご予算、納期に合わせて最適な進め方をご提案します。はじめての方にもわかりやすい説明を心がけ、公開後の運用や集客まで一貫してサポート可能です。まずは気軽にお声がけください。
- 現状ヒアリングと課題の可視化
- 目的別の進め方と概算費用提示
- スケジュール案と体制のご提案
- 公開後サポートと改善方針の共有
- 他社見積との比較観点アドバイス
人気の関連資料のご案内
準備をスムーズに進められるよう、無料のチェックリストやテンプレートをご用意しています。制作前の要件定義シート、原稿作成の見出しテンプレ、SEOの基本チェックなど、すぐに実務で使える内容です。ダウンロードして社内共有し、共通認識づくりにお役立てください。
- 中小企業のウェブマーケティングロードマップ
- 今のホームページで大丈夫?ホームページ診断チェックリスト
- 採用×ホームページ|自社にあった人材を採用するためのコンテンツ戦略ガイド
- 基礎からわかるWebマーケティング入門ガイド
ホームページのサブスクという選択肢も
最近ではホームページのサブスクサービスも出てきており、高いデザイン性やクオリティのサイトがコストを押さえて運用することができるようになりました。
ウィルサポは月額9,800円からオリジナルのホームページをもてるサブスクサービスです。
SEO面もしっかりと対策した上で、お客様のビジネスの成長をサポートさせていただきます。LP制作や新規サイトはもちろん、サイトのリニューアルにも対応しております。
- 初期費用なしで月額9,800円から
- フルオーダーでデザイン作成
- サーバー、ドメイン費用無料
- サイトの保守費用無料
- 契約期間の縛りなし
- 集客サポートプランあり