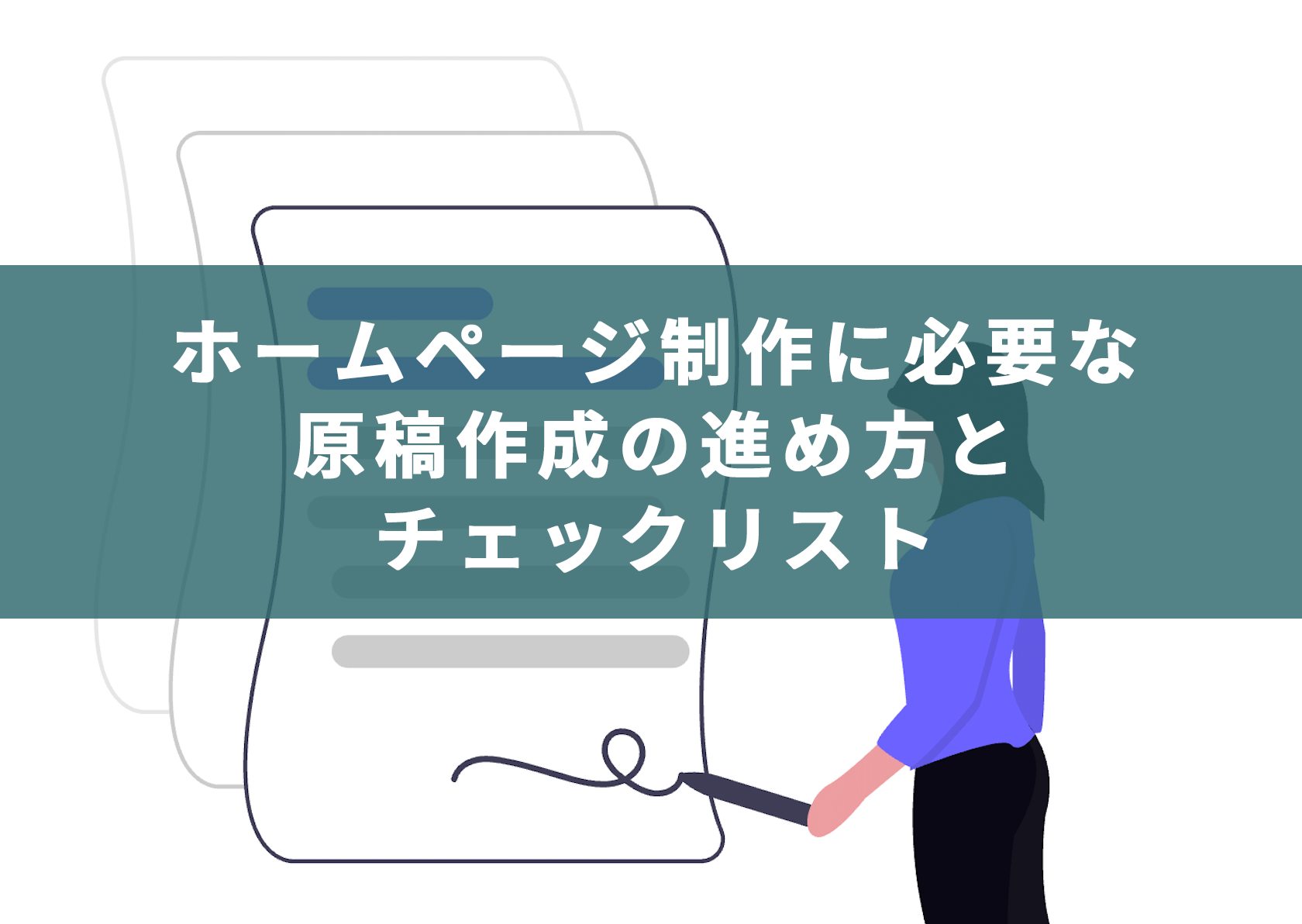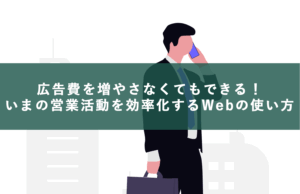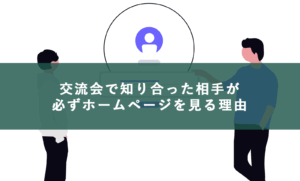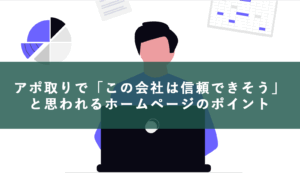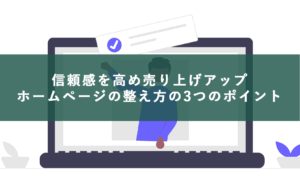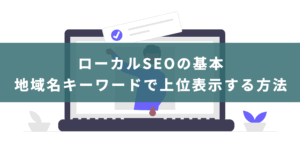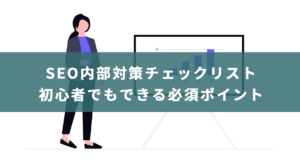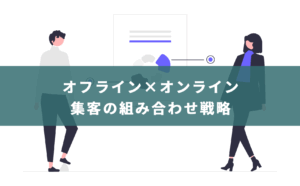こんな方におすすめの記事です
- 原稿作成の始め方を基礎から丁寧に知りたい
- 担当になったが全体の進め方が分からない
- 何を書けば良いか具体例と型がほしい
- 見積前に準備物と範囲を整理したい
- 社内確認しやすいチェック表がほしい
- 文章が苦手でも迷わず形にしたい方法
- 制作会社へ渡す資料の整え方を知りたい
この記事でわかること
- 原稿作成の五つの手順と要点が分かる
- 情報の集め方と社内ヒアリングの方法
- ページ構成と見出しの作り方のコツ
- 文章を分かりやすくする具体テクニック
- 写真・図・権利の準備と注意点の基礎
- 検索に強い原稿の基本と簡単SEOルール
- 公開前チェックと入稿の流れと段取り
はじめに(この記事でできること)
こんな方向けの記事です
本記事は、Webの知識が少ない中小企業の経営者・担当者向けに、原稿作成の進め方をやさしく解説します。難しい用語を避け、準備から入稿までを「何を集め、何を書くか」の順で具体化。読めば、いつ誰が何を用意し、どの状態で制作会社へ渡すかが明確になります。社内共有や稟議にも使える内容です。
読み方ガイド
最初から通して読めば全体像を短時間で把握できます。急ぎの方は「全体像→構成→テンプレ→チェック」の順が効率的。いま困っている箇所だけ拾い読みしても成立します。各章は独立しており、最後に作業が進む“次の一手”が分かる設計です。手元の原稿に当てはめながら読み進めてください。
「中小企業のWebマーケティング|戦略ロードマップ」
無料ダウンロード資料配布中
【こんな方におすすめ】
- Webからの集客を増やしたいが、どの施策が効果的かわからない
- ホームページやSNSを活用しているが、問い合わせや売上につながらない
- 少ない予算・人員でも実践できるWebマーケティングの方法を知りたい
【この資料でわかること】
- 中小企業が成果を出すためのWebマーケティングの基本と成功ステップ
- 「アクセスが増えない」 「問い合わせが少ない」など、よくある課題の解決策
- 限られたリソースでも実践できる、最新のデジタルマーケティング手法
原稿作成の全体像(5つのステップ)
ステップ1 準備(目的・ターゲット決め)
まず「問い合わせを増やす」「採用応募を増やす」など目的を一つに絞ります。次に、誰に読んでほしいかを一文で定義し、悩みと判断基準を箇条書きで整理。ここで決めた軸が、見出しや写真選びの方針になります。準備が曖昧だと下流で迷いが増え、時間とコストが膨らむので最初に固めましょう。
ステップ2 情報集め(ヒアリング・資料)
営業・現場・サポートから、事例、数字、よくある質問、写真の在庫を集めます。お客様が選んだ理由や失注の理由も重要な素材です。許諾の必要有無を同時に確認し、後の差し替えを防ぎます。集めた情報はフォルダで分類し、出典をメモ。一次情報を多く集めるほど信頼性が上がります。
ステップ3 構成づくり(見出し案・流れ)
ページごとに「結論→根拠→行動(CTA)」の流れで見出しを並べます。トップ、サービス、事例、会社、FAQ、問い合わせの基本線を先に決め、重要順に優先度を設定。各見出しには、読み手の疑問に答える短い要約を添えましょう。構成が固まれば、執筆は“空欄を埋める作業”に変わります。
ステップ4 書く(テンプレに当てはめる)
用意したテンプレに沿って、結論を先に書き、根拠は数字や事例で短く補足。専門用語は言い換えを添え、長文は段落で分けます。写真や図で補える箇所は文章を削って見やすく。まず七割の完成度を目指し、関係者でレビューして不足を埋めます。完璧主義より早く形にし、改善を回すのが近道です。
ステップ5 見直す(チェック→入稿)
誤字脱字、数字、固有名詞、権利、リンク先をチェックし、CTAや電話・フォームの導線も確認。画像サイズと代替テキストを整え、ファイル名や見出しのルールを最終調整します。修正箇所は履歴を残し、制作会社へ渡すフォルダ構成に沿って入稿。検収の観点を共有すると手戻りが減ります。
作る前の準備(目的・ターゲット・強み)
目的を一つに絞る(例:問い合わせ増)
目的が多いとメッセージが弱くなります。最優先を一つ決め、他は二次目標として扱いましょう。「問い合わせ◯件」「資料請求◯件」など数字で置くと判断が早まります。目的が決まれば、必要なページやCTAの位置、写真や実績の出し方も自ずと決まります。まず“何のために書くか”を明確に。
誰に読んでほしいかを一文で定義
「地元で店舗改装を検討するオーナー。予算と納期が不安」など、一文で人物像と悩みを表現します。検索しそうな言葉、決め手になる情報も添えると見出しが作りやすくなります。読み手が変われば言葉と順番も変わります。誰に向けて書くのかを最初に決め、全員で同じ前提を共有しましょう。
自社の強みを三つに整理(根拠もセット)
強みは三つに絞って覚えやすく。価格、品質、速度、サポートなどから選び、数字や事例で裏付けます。「施工実績◯件」「再依頼率◯%」のように根拠を短く提示。強みが多すぎると印象が薄まります。差が出ない項目は捨て、選ばれる理由が一目で伝わる構成に整えましょう。
情報を集める(社内ヒアリングと資料)
ヒアリングの質問例(悩み・選ばれた理由)
営業や現場に「最初の相談内容」「比較された相手」「決め手になった一言」を聞きます。お客様の声は実名・匿名の許諾も確認。よくある反論と回答はFAQに活用します。失注理由は改善の宝です。社内の生の声を集めるほど、読み手に刺さる原稿になります。記録はフォームで統一しましょう。
事例・数字の集め方(写真・実績の許可)
事例は「課題→施策→効果」の順で短く整理し、前後写真や数値を添えます。売上やコストの数字は出典と期間を明記。掲載許可と写真の権利も同時に確認し、後日の差し替えを防ぎます。数字が難しい場合は、作業時間の短縮や満足度など別指標を使い、効果を具体的に伝えましょう。
競合サイトの見方(良い所/直す所の把握)
競合三社を絞り、トップの訴求、事例の見やすさ、問い合わせ導線を観察。良い所は採り入れ、伝わりにくい所は逆に差別化ポイントです。価格や実績の出し方、写真の雰囲気も比較。自社の読み手にとって分かりやすい順番に直すだけでも、一歩抜け出せます。学びを自社構成へ反映しましょう。
構成を決める(サイトマップとページ構成)
必要ページの洗い出し(トップ〜問い合わせ)
基本は「トップ/サービス/事例/会社情報/FAQ/問い合わせ」。採用や料金が重要なら追加します。各ページの役割を一言で定義し、重複は統合。更新が必要なページはCMSで楽に編集できるよう前提を作ります。最初に全体の箱を決めると、抜け漏れが減り、制作と運用がスムーズになります。
ページ内の並び順(結論→根拠→行動)
最初に「一番伝えたい結論」を短く示し、すぐ下で根拠や事例を提示。最後は「見積を依頼」「資料を請求」など行動のボタンへつなげます。スマホではスクロールが基本なので、重要要素は上にまとめるのが鉄則。迷いを減らす順番が、成果を押し上げます。各段落は一つの話題に絞りましょう。
見出し(H2/H3)の作り方と文字数目安
見出しは「読み手の疑問に即答する言い方」にします。例「料金は?」「選ばれる理由」「導入手順」。長すぎる見出しは要点を二つに分割。本文は三〜四文で一段落にまとめ、空白を活かして読みやすく。見出しだけを眺めても内容が通じると、全体の理解が早まり、離脱も減ります。
ページごとの書き方(ひな形テンプレ)
トップページの型(価値・実績・CTA)
冒頭で「誰に何を提供する会社か」を一文で提示。続けて実績やお客様の声で信頼を補強し、主要サービスの入口を分かりやすく配置します。迷わず行動できるよう、資料請求や見積依頼のCTAを各所に配置。旬の情報やキャンペーンは目立つ場所へ。更新しやすい構成にして鮮度を保ちましょう。
サービスページの型(課題→解決→料金)
読み手の課題を最初に示し、自社の解決策を図と短文で説明。強みは三点に絞り、他社との違いを具体例で伝えます。料金は条件と範囲を明記し、よくある不安にはFAQで先回り。導入手順や納期も簡潔に。最後は事例やCTAへ自然に誘導し、相談のハードルを下げましょう。
会社紹介の型(信頼情報・沿革・体制)
代表挨拶は「約束する価値」を短く。所在地、免許、取引実績、受賞、取引銀行などの信頼情報を一覧で。沿革で歴史と強みの背景を示し、組織体制と担当者の顔が見える写真を掲載。採用や協業の窓口も明確に。誇張より事実の積み重ねが信頼を生みます。更新日も記して新しさを伝えましょう。
事例ページの型(課題→施策→効果)
「どんな課題に対して、何をして、どう良くなったか」を同じ型で並べます。ビフォー・アフターの写真、期間、担当、使用ツール、数値効果を簡潔に。固有名詞と許諾の確認を忘れずに。型が揃うと比較しやすく、説得力が増します。最後に関連サービスや問い合わせへ誘導すると効果的です。
FAQ・問い合わせページの型(不安解消)
「料金の目安」「納期」「対応エリア」「キャンセル」など、連絡前に不安な点を先に解消します。問い合わせフォームは項目を絞り、電話とメールの両方を用意。送信後の自動返信と返答予定も明記すると安心です。地図や営業時間も忘れずに。連絡しやすさは、そのまま件数に影響します。
わかりやすい文章のコツ
短い文で結論先出し(主語と動詞を近く)
一文は短く、結論を先に書きます。主語と動詞を近づけ、修飾語を増やしすぎないことが読みやすさの基本です。段落の最初に要点を書き、次に理由と例を添えるだけで伝わり方が変わります。迷ったら「誰が・何を・どうする」を先に書く。余分な言い回しは削って、シンプルに整えましょう。
専門用語は言い換え+例えを添える
専門用語は、身近な言葉に言い換え、短い例えを添えると理解が早まります。例えば「CMS=更新を簡単にする仕組み」のように、先に結論で意味を示すのがコツです。難しい表現を積み重ねるより、日常の言葉で具体的に。読者がその場で判断できる説明を心がけましょう。
箇条書きと表で“見てわかる”にする
重要点は三〜五項目で箇条書きに。比較は表にすると一目で違いが伝わります。文章だけで説明しようとすると長くなり、読み手は途中で離脱します。図や写真で置き換えられる箇所は迷わず置換。視覚情報を増やすほど理解は早まり、記憶にも残ります。見やすさは説得力そのものです。
写真と図の用意(撮影 or 素材/指示書)
何を撮るかリスト化(人・現場・製品)
人物(代表・担当・お客様)、現場の作業風景、製品・成果物、会社外観・内観を撮ると信頼につながります。用途(トップ用/事例用)を明記し、必要枚数と構図を先に決めると無駄撮りを防げます。スマホ撮影でも、光と背景を整えれば十分使えます。権利と許諾は事前に確認しましょう。
撮影指示書の作り方(用途・構図・点数)
指示書は「使う場所」「ねらい」「構図」「点数」「被写体の名前」を一枚に整理。横位置と縦位置の両方を指定し、余白を多めに撮るとレイアウトしやすくなります。当日の担当と時間割、注意事項も記載。事前に共有しておけば、撮影当日は迷いなく進行でき、後の差し替えも少なくなります。
素材サイトの使い分けと権利の基本
写真素材は「商用可」「クレジット表記」など利用条件を必ず確認。人物写真はモデルリリースの有無も要注意です。無料素材は便利ですが、他社と被りやすい点を理解しましょう。ブランドの要所は自社撮影、汎用部分は素材活用が現実的。ダウンロード元とライセンス情報は記録を残します。
検索で見つけてもらう基本(SEOの基礎)
キーワードの決め方(お客様の言葉で)
お客様が実際に検索しそうな言葉から決めます。「地域名+サービス名」「悩み+解決策」など、三〜五語を候補化。社内の呼び名ではなく、外の人の言葉を優先しましょう。ページごとに主役の言葉を一つに絞ると、内容がぶれません。営業や問い合わせ履歴は、貴重なヒントの宝庫です。
タイトル・見出し・本文への入れ方
主役の言葉は、ページタイトル、最初の見出し、本文の前半に自然に入れます。無理な詰め込みは逆効果。関連語や言い換えで読みやすさを保ちましょう。画像の代替テキストやリンク文言も意味が通る表現に。検索と人の読みやすさを両立させることが、結果として成果に直結します。
重複回避と内部リンクの簡単ルール
同じ内容を複数ページに重ねると評価が分散します。近い話題は一つにまとめ、関連ページへ内部リンクでつなぎます。「詳しくはこちら」ではなく、内容が分かる文言でリンクしましょう。トップやサービス、事例、問い合わせの回遊を意識すると、読者も迷わず、サイト全体の評価も安定します。
表記ルールと用語統一(ガイドの作り方)
数字・単位・日付の書き方を統一
「半角/全角」「円表記」「日付の区切り」など、表記を一度決めて最後まで揃えます。例:半角数字、税込表記、日付はYYYY/MM/DD。統一されているだけで、読み手の安心感が増し、誤解も減ります。社内ガイドに記し、外部パートナーとも共有しましょう。迷ったら実例を添えるのがコツです。
言い回し・敬語のレベルをそろえる
語尾が「です・ます」と「だ・である」で混在すると印象が不安定になります。基本のトーンを決め、例外を最小限に。社名や商品名の表記も固定し、略称の使い方を明記します。読み手に失礼のない丁寧さを保ちつつ、回りくどい表現は削る。気持ちよく読める文体が信頼を生みます。
禁則事項とNGワードのメモを作る
根拠のない最上級表現、差別的・誤解を招く言い方、誤記しがちな固有名詞は、事前にNGとして一覧化。法律や業界ルールに触れる可能性がある表現はチェックフローに回します。禁止だけでなく、推奨の言い換え例も併記すると運用が楽です。小さな事故を未然に防ぐ仕組みを作りましょう。
チェックリスト(公開前の最終確認)
誤字脱字・数字・権利の最終チェック
固有名詞、金額、単位、期間、リンク先、引用の出典を最終確認。写真や図の権利、掲載許諾、クレジット表記の要否も見落としなく。第三者の目で読むと精度が上がります。チェックは役割分担し、完了の印を残しましょう。ここでの一手間が、公開後の差し替えやトラブルを大きく減らします。
CTA・電話・フォーム導線の確認
ページごとに「次に取ってほしい行動」が明確かを点検。電話ボタンは発信画面が開くか、フォームは入力→送信→自動返信まで通しで試験します。必須項目は必要最小限にし、スマホのキーボード種別も最適化。導線の迷いはそのまま機会損失です。公開直前に複数人で再確認しましょう。
画像サイズ・代替テキストの確認
画像は表示サイズに合わせて最適化し、重いデータは圧縮。代替テキストは、画像の意味が伝わる短文にします。装飾画像は空にして読み上げの邪魔を防止。ファイル名は内容が分かる英数字で統一すると管理が楽です。見た目だけでなく、速さとアクセシビリティも同時に満たしましょう。
原稿の渡し方(制作会社への共有方法)
ファイル構成の例(フォルダと命名ルール)
ルートに「原稿」「画像」「図」「資料」「許諾」を作成。ページごとに番号を付け、原稿は「01_top.md」など統一名で保存します。画像は用途別に「top」「service」などフォルダ分け。版数は「v1」「v2」と履歴化。誰が見ても迷わず使える構成が、制作のスピードと品質を高めます。
コメントと修正履歴の残し方(誰がいつ)
修正はコメント機能で「理由→対応→担当→期日」を記録。完了したら解決に変更し、履歴を残します。電話や口頭の指示は要点を文書化し、同じフォルダに格納。誰がいつ何を直したかが追えるだけで、手戻りや認識違いは大幅に減ります。決め事は同じ場所に集約するのがコツです。
受け渡し後の確認フロー(校正→公開)
受領後は制作側で体裁を整え、ステージ環境で校正。指摘はラウンド制でまとめ、締切を切って反映します。公開前に最終チェックリストを実施し、OKなら本番へ反映。公開直後はフォームやリンクの再確認と、サイトマップ送信まで一気に実施。初週は不具合の監視と軽微修正を素早く回します。
無料相談のご案内
制作やリニューアルで迷ったら、専門家に相談するのが近道です。ご要望やご予算、納期に合わせて最適な進め方をご提案します。はじめての方にもわかりやすい説明を心がけ、公開後の運用や集客まで一貫してサポート可能です。まずは気軽にお声がけください。
- 現状ヒアリングと課題の可視化
- 目的別の進め方と概算費用提示
- スケジュール案と体制のご提案
- 公開後サポートと改善方針の共有
- 他社見積との比較観点アドバイス
人気の関連資料のご案内
準備をスムーズに進められるよう、無料のチェックリストやテンプレートをご用意しています。制作前の要件定義シート、原稿作成の見出しテンプレ、SEOの基本チェックなど、すぐに実務で使える内容です。ダウンロードして社内共有し、共通認識づくりにお役立てください。
- 中小企業のウェブマーケティングロードマップ
- 今のホームページで大丈夫?ホームページ診断チェックリスト
- 採用×ホームページ|自社にあった人材を採用するためのコンテンツ戦略ガイド
- 基礎からわかるWebマーケティング入門ガイド
ホームページのサブスクという選択肢も
最近ではホームページのサブスクサービスも出てきており、高いデザイン性やクオリティのサイトがコストを押さえて運用することができるようになりました。
ウィルサポは月額9,800円からオリジナルのホームページをもてるサブスクサービスです。
SEO面もしっかりと対策した上で、お客様のビジネスの成長をサポートさせていただきます。LP制作や新規サイトはもちろん、サイトのリニューアルにも対応しております。
- 初期費用なしで月額9,800円から
- フルオーダーでデザイン作成
- サーバー、ドメイン費用無料
- サイトの保守費用無料
- 契約期間の縛りなし
- 集客サポートプランあり