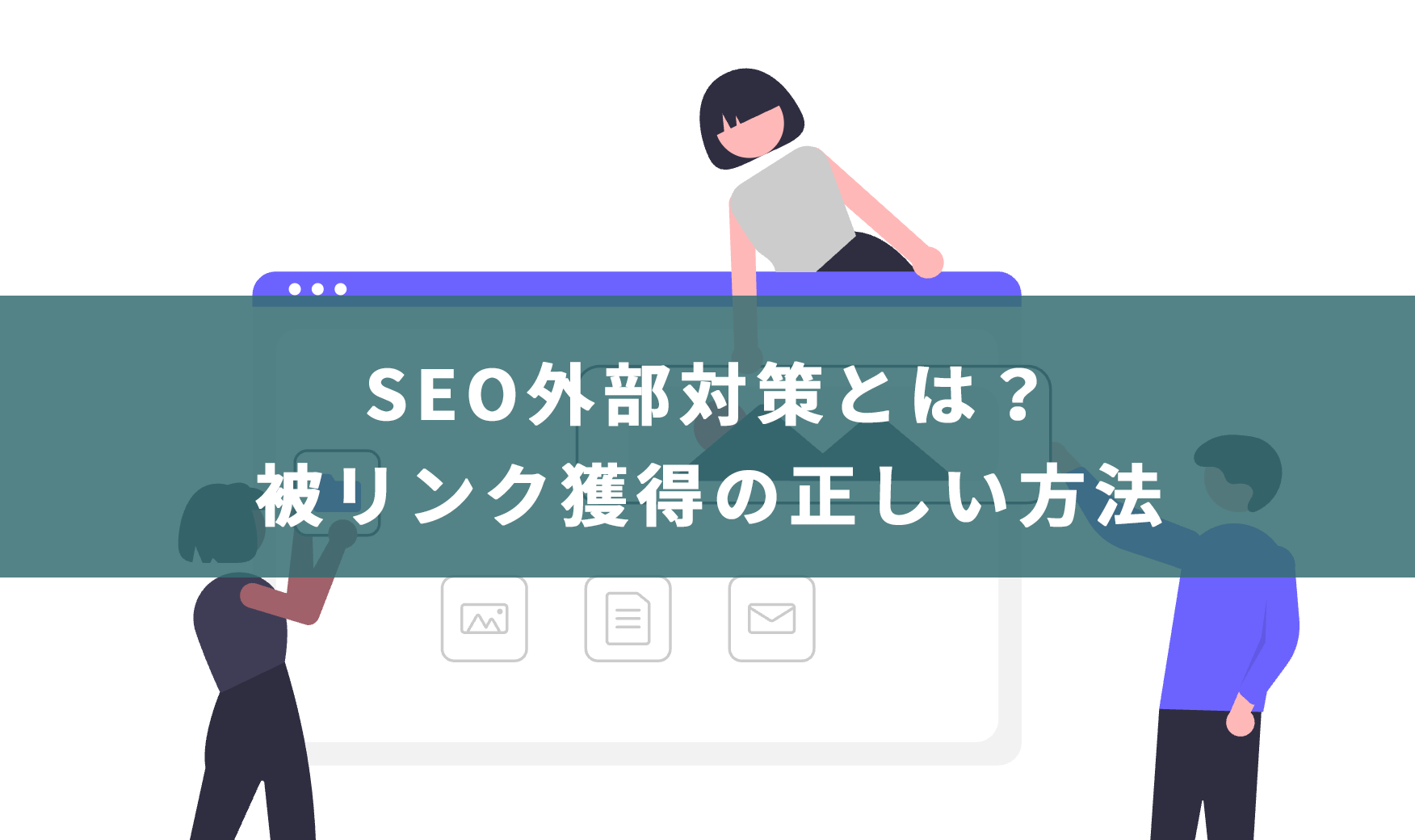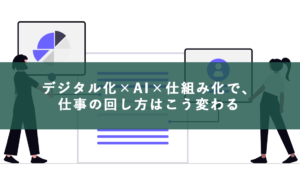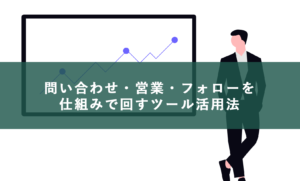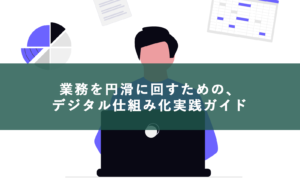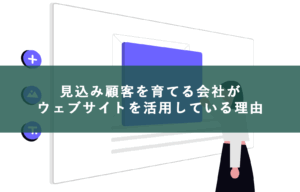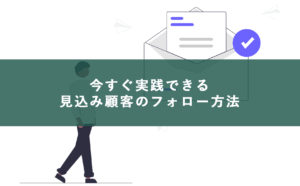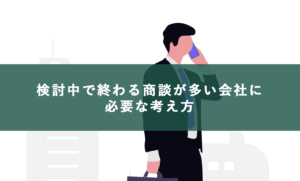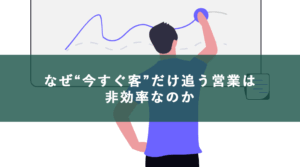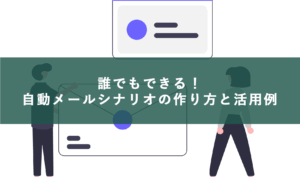SEO外部対策とは?被リンク獲得の正しい方法
はじめに
外部対策とは、他サイトから自社サイトへ向けたリンク(被リンク)を増やし、検索エンジンと読者に「役立つ情報源だ」と伝える取り組みです。大切なのは数を無理に増やすことではなく、関連性が高く、信頼できるサイトから自然に紹介される状態を作ること。この記事では、基礎の考え方から実践の手順、連絡文面の作り方、効果測定とリスク回避までをわかりやすく整理します。今日から始められる具体策に落として解説します。
こんな方におすすめの記事です
- 被リンクの基礎が曖昧で不安
- 安全な獲得方法を知りたい
- プレスリリース活用に迷っている
- 寄稿や提携の進め方が不明
- ローカル対策を強化したい
- 効果測定のKPIが定まらない
- スパム判定の回避策を学びたい
- 社内運用の型を整えたい
- 営業と広報の連携が弱い
- 短期と中長期の配分で悩む
この記事でわかること
- 外部対策の役割と考え方
- 良い被リンクの条件と基準
- 戦略設計とターゲット設定
- コンテンツ起点の具体策
- デジタルPRと寄稿の進め方
- 提携・事例相互掲載の型
- ローカル名簿登録の手順
- 連絡文面と運用ルール
- KPI設計と評価方法
- ガイドラインとリスク回避
「中小企業のWebマーケティング|戦略ロードマップ」
無料ダウンロード資料配布中
【こんな方におすすめ】
- Webからの集客を増やしたいが、どの施策が効果的かわからない
- ホームページやSNSを活用しているが、問い合わせや売上につながらない
- 少ない予算・人員でも実践できるWebマーケティングの方法を知りたい
【この資料でわかること】
- 中小企業が成果を出すためのWebマーケティングの基本と成功ステップ
- 「アクセスが増えない」 「問い合わせが少ない」など、よくある課題の解決策
- 限られたリソースでも実践できる、最新のデジタルマーケティング手法
外部対策(被リンク)の基本
外部対策の目的は、第三者からの「推薦」を増やし、信頼と発見性を高めることにあります。被リンクは検索評価の多くの要素の一つですが、質が悪いリンクを増やすと逆効果になることもあります。まずは内部対策で内容と導線を整え、その上で関連性の高い媒体から自然に紹介される仕組みを作るのが安全で継続的です。量より質、短期より継続、作為よりも「役立つから引用された」という状態を目指しましょう。
外部対策の役割と内部対策との違い
内部対策は自社の努力だけで改善できますが、外部対策は他者からの評価が必要です。だからこそ、内容の価値と使いやすさが前提になります。良い外部対策は、まず役立つ記事や資料、比較表、調査など「紹介したくなる理由」を用意し、それを記者・編集者・業界団体・パートナーへ分かりやすく届ける設計から始まります。内部で土台を整え、外部で広げる。両輪がそろうと、検索でも紹介でも安定した成果につながります。
- 内部で価値と導線を整備する
- 紹介される理由を明文化する
- 対象媒体の関心を調査する
- 一次情報の素材を用意する
- 短期と継続の配分を決める
- 営業と広報の連携を強化する
- 反応の出所を可視化管理する
- 勝ち型をテンプレ化して展開
良い被リンク・悪い被リンクの見分け方
良い被リンクとは、内容の関連性が高く、信頼できる運営主体から、文脈に沿って自然に設置されたリンクです。媒体の読者にとって価値があり、リンク先の内容とアンカーテキストが一致していることが大切です。逆に、金銭で購入したリンク、無関係な大量の相互リンク、機械的に量産された記事からのリンクはリスクになります。評価は「誰が」「どこで」「何のために」紹介したのかを軸にし、短期の数量に惑わされない判断を徹底しましょう。
- 媒体の運営者と読者像を確認
- 記事文脈とリンク意図を一致
- アンカー文を具体表現に調整
- 金銭提供リンクの回避を徹底
- 無関係な相互リンクを禁止
- 量産スパムサイトを避ける
- 紹介理由を記録して可視化
- 質重視のKPIで運用管理
正しい被リンク獲得の考え方
被リンクはお願いだけでは集まりません。「紹介する側のメリット」が明確であること、そして提供する情報に独自性や便利さがあることが前提です。ターゲット媒体と読者のニーズを把握し、どの切り口なら取り上げやすいかを設計します。さらに、成果の測定や運用体制を最初に決め、担当と期限、記録方法を整えると、継続的に改善できます。
戦略設計:ターゲットと訴求の明確化
まず、誰に紹介してほしいのかを具体化します。業界メディア、地域紙、商工会、パートナー、インフルエンサーなど、媒体ごとに関心テーマと掲載基準が違います。自社の強みを「数字」「事例」「手順」「テンプレ」など編集しやすい形に変換し、先方の読者にとっての利益を先に提示しましょう。ニュース性(新しい・比較できる・役立つ)を言語化し、いつ・誰が・どの素材でアプローチするかを計画に落とします。
- 媒体ペルソナと読者像を定義
- 自社の強みを数字で言語化
- 事例と比較表を事前に整備
- ニュース性の要素を三点化
- 訴求テーマを四半期で計画
- 担当・期限・素材を紐づける
- 不採用時の代替案を用意
- 狙いと想定見出しを明記
コンテンツ起点での獲得
「紹介したくなるコンテンツ」を用意すると、自然なリンクが増えます。おすすめは、調査レポート、統計の可視化、業務テンプレート、ハウツー、事例集、業界用語集など、取材や引用に使いやすい素材です。ダウンロード可・引用条件明記・画像や図表の二次利用可など、使う側の手間を減らす工夫も重要。内容は更新を続けて鮮度を保ち、季節や法改正といったタイミングに合わせて再発信しましょう。
- 調査設計と質問票を公開する
- 図表付きの要約版を用意する
- テンプレ資料を配布可能にする
- 引用条件と表記例を明記する
- 更新頻度と改訂履歴を公開
- 季節・法改正の特集を組む
- 関連ページへ文脈リンクを張る
- SNSで引用例を紹介促進する
実践的な獲得手法
外部対策の王道は、デジタルPR、提携・相互掲載、名簿・ローカル登録、寄稿・共同研究、リンク切れや未リンクの回収、取材対応の仕組み化です。無理な量産や購入は避け、相手の読者利益を中心に据えましょう。各手法はテンプレ化し、再現性の高い型として運用すると効率が上がります。
デジタルPR(プレスリリース・寄稿)
ニュース性のある話題を「誰に」「どの切り口で」届けるかが鍵です。新機能の発表だけでなく、調査結果、業界の課題と解決策、成功事例の定量的なまとめなど、編集しやすい素材を提供しましょう。配信前に、見出し・要約・図表・引用タグ・写真代替テキストまで整えると掲載確率が上がります。寄稿は媒体の編集方針に合わせ、広告色を抑え、読者の役に立つ一次情報で信頼を積み上げます。
- 配信媒体の編集方針を確認する
- 見出しと要約を先に作成する
- 図表と画像の代替文を用意
- 引用OKの表記を明示して提示
- 広告色を抑え一次情報で勝負
- 掲載後は関連記事へ誘導する
- 不採用理由を学びに変換する
- 寄稿の定例枠を獲得継続する
アライアンス・パートナー施策
相性の良い企業と協力し、共同セミナーや共同資料を公開すると、双方のサイトに自然な相互リンクが生まれます。役割分担と編集基準を事前に決め、事例ページで互いに紹介することで、読者にとっても比較検討がしやすくなります。業界団体や商工会の紹介枠も活用し、第三者の信頼を借りるのも有効です。公開日は合わせ、SNSやメルマガで同時に告知して広がりを作りましょう。
- 補完関係の強い企業を選定する
- 共同資料の編集基準を合意する
- 事例ページで相互に紹介掲載
- 公開日と告知計画を同期する
- 商工会や団体の枠を活用する
- 申込導線を双方サイトで整備
- 成果を四半期で振り返り改善
- 次回テーマを先に決め継続化
ディレクトリ・ローカルリスティング
信頼できる業界名鑑やローカル名簿(Googleビジネスプロフィール等)は、基本の整備だけでも効果があります。社名・住所・電話(NAP)の統一、カテゴリ選択、営業時間、商品説明、写真、口コミの返信など、公式情報をそろえましょう。真偽不明の名簿への大量登録は避け、関連性と思わぬリスクを見極めます。地域性の高い事業ほど、地元メディアや行政サイトの紹介ページを丁寧に整備することが信頼につながります。
- NAP情報を全媒体で完全統一
- 適切なカテゴリを正しく選定
- 営業時間と説明文を最新化する
- 写真と商品情報を充実掲載
- 口コミへ丁寧に返信を継続する
- 不要名簿の登録を避ける判断
- 行政・地元サイトの掲載を確認
- 変更履歴を台帳で一元管理する
ゲストポストと共同研究
媒体への寄稿(ゲストポスト)や共同研究の公開は、専門性を示しつつ自然なリンクを得られる手段です。相手媒体の編集方針に合わせ、読者課題の解決に集中した内容にします。共同研究はデータの収集方法を明示し、再現性のある手順で信頼を担保。図表や原データの提供、著者プロフィール、監修情報を整えると引用されやすくなります。成果は自社サイトで要約し、詳細は媒体に誘導する二段構成が有効です。
- 媒体の編集基準を読み込む
- 読者課題中心の構成へ修正
- 調査手法と対象を明確に記載
- 図表と原データを公開準備
- 著者と監修情報を整備提示
- 要約記事で媒体へ誘導設計
- 再利用可能な素材を同梱する
- 掲載後の反応を共有し改善
ブロークンリンク・アンリンク回収
他サイトのリンク切れ(ブロークン)に対し、代替となる自社コンテンツを丁寧に提案すると、相手の助けになりつつリンク獲得が狙えます。また、自社名が記事で言及されているのにリンクが無い(アンリンク)ケースは礼儀正しく依頼すると改善されることがあります。重要なのは、相手読者の利便性を第一に、根拠とメリットを簡潔に示すこと。テンプレ文面と追跡表で運用を回しましょう。
- 言及記事を定期的にモニタする
- 代替URLの価値を簡潔に説明
- 相手読者の利益を先に提示
- 丁寧な依頼文と期限を明記
- 未返信時の再送ルールを定義
- 対応状況を台帳で管理共有
- 改善後に感謝の連絡を送付
- 学びをテンプレへ反映更新
取材対応・Q&Aプラットフォーム
メディアの取材募集や専門家コメントを集めるプラットフォームに素早く回答すると、掲載とリンクの機会が増えます。社内で「回答できる領域」「実績」「写真・プロフィール」「引用可の図表」をあらかじめ用意し、一次回答のスピードを上げましょう。取材後は記事公開に合わせて自社でも紹介し、読者導線を整えます。継続利用で記者との関係が生まれ、次の相談にもつながります。
- 回答可能な領域を一覧化する
- プロフィールと写真を整備する
- 図表素材を事前に準備しておく
- 一次回答のSLAを社内で設定
- 掲載後の紹介記事を用意する
- 記者連絡先を台帳で管理する
- 反応データを毎月レビュー
- 成功事例を横展開で共有する
アウトリーチの作法と体制
連絡(アウトリーチ)は、相手の読者利益を中心に、短く具体的に提案することが基本です。件名、要点、読者メリット、引用素材、希望掲載箇所の候補まで用意すると意思決定が早まります。属人化を避け、テンプレと台帳、再送ルール、期限管理を仕組みに落とし込みましょう。
連絡文面・提案内容の最適化
第一通は「相手が得をする理由」を先に書き、100〜200字で要点をまとめます。本文では、想定見出し・引用可能な数字・図表リンク・掲載候補の章節を提示し、必要なら執筆や監修の協力も申し出ます。自社の宣伝が強すぎると敬遠されるので、読者にとっての利点と取材のしやすさを優先。返信があったら即時に素材を渡せる準備をしておきましょう。無理な追い込みは禁物、丁寧さと継続が成果を生みます。
- 件名で読者メリットを明示する
- 要点を200字以内で簡潔記述
- 想定見出しを二案ほど提示
- 引用可能な数字と図表を添付
- 掲載候補の章節を提案する
- 返信直後に素材を即時提供
- 再送間隔と回数をルール化
- 断りへの感謝で関係を維持
運用ルールと記録管理
媒体リスト、担当、連絡履歴、反応、掲載URL、リンク属性、掲載位置を一元管理すると、ムダ打ちが減ります。四半期ごとに勝ち筋(媒体×ネタ×文面)を確認し、テンプレを更新。CRMやスプレッドシートでも十分運用できます。社内で広報・営業・制作が同じ台帳を見る体制にすると、情報が止まらず、機会損失を防げます。
- 媒体と担当の一覧を整備共有
- 連絡履歴と結果を時系列管理
- 掲載URLと属性を必ず記録
- 勝ち筋の型を四半期で更新
- 重複連絡を防ぐ責任分担化
- 台帳を全員が同じ場所で運用
- 学びを定例会で共有展開する
- 退職時の引継手順を明文化
評価・測定・ガイドライン
外部対策の評価は「数」だけでなく「質」と「事業への貢献」で見ます。参照トラフィック、CVへの寄与、媒体の関連性、掲載位置、アンカーの適切さなどを総合評価し、投資配分を調整します。あわせて、検索エンジンのガイドラインに沿い、リスクの高い手法は避けましょう。
効果測定とKPI
KPIは「被リンク数」より「参照トラフィック」「CV貢献」「掲載媒体の質」を重視します。短期は掲載数やクリック、長期は自然検索の成長とブランド指名増加を合わせて見ると全体像がつかめます。媒体別・テーマ別・文面別の比較で勝ち筋を特定し、次の四半期に資源を寄せる運用が効率的です。数字は月次で一枚にまとめ、関係者で意思決定を早く回しましょう。
- 参照トラフィックの推移を計測
- CVと間接貢献を可視化する
- 媒体の質と関連性を評価する
- 掲載位置とアンカーを点検する
- テーマ別の反応差を比較分析
- 四半期で配分を最適化更新
- 月次一枚資料で意思決定促進
- 勝ち筋をテンプレ化して展開
ガイドライン遵守とリスク管理
有料リンク、過剰な相互リンク、リンク目的の自演ネットワーク(PBN)は避けるべきです。発見されにくいからといって続けると、評価の低下や検索除外のリスクがあります。リンク否認ツールは最後の手段であり、まずは問題リンクの削除依頼と内部の改善が先。社内ルールを作り、外部委託時も契約に「不正手法の禁止」を明記しておきましょう。安全第一の運用が長期の成果につながります。
- 有料・過剰相互リンクを禁止
- PBNなど自演網は採用しない
- 問題リンクは削除依頼を実施
- 否認は最終手段として判断
- 代理店契約に禁止条項を明記
- 社内ルールを文書で共有する
- 定期監査で早期に兆候発見
- 安全性を最優先で運用継続
社内で進めるためのチェックリスト
成果を出すコツは、月次で「計画→実行→記録→学び」の小さな循環を回すことです。コンテンツ計画とPRトピック、連絡数と返信率、掲載の質を定例で見直し、次の三手を決めます。属人化を避け、誰が見ても進捗と次の行動が分かる台帳運用にしましょう。
月次運用の型
月初にテーマと素材を決定し、週次でアウトリーチ、月末に結果を集約して改善点を三つに絞ります。勝ち素材は再発信や別媒体向けに編集し直し、負けは原因を特定して撤退または改良へ。営業・広報・制作が同じ場でレビューし、翌月の担当と期限を確定。小さな成功を積み上げる設計で、被リンクと参照流入を安定的に伸ばしていきます。
- 月初にテーマと素材を決定する
- 週次で連絡数と返信率を点検
- 掲載の質と位置を評価記録する
- 勝ち素材を再編集して展開
- 負けの要因を仮説で特定する
- 翌月の三手を合意し責任化
- 台帳を最新状態に保ち共有
- 四半期で戦略をアップデート
まとめ
外部対策の本質は「役立つから自然に紹介される」状態づくりです。内部で価値と導線を整え、外部へは読者利益を軸に丁寧に届ける。デジタルPR、提携、名簿整備、寄稿、回収、取材対応を型にして回し、質で評価されるリンクを積み上げましょう。KPIは質と貢献で管理し、危険な近道は選ばない。今日できる一歩として、紹介されやすい一本の資料と、連絡テンプレ・台帳の準備から始めてください。
- 内部の価値と導線をまず整える
- 読者利益起点で提案を設計する
- デジタルPRの型を運用開始する
- 提携と事例相互掲載を仕組み化
- ローカル名簿情報を最新に保つ
- 寄稿と共同研究で専門性を示す
- 未リンクとリンク切れを回収する
- KPIは質と貢献で意思決定する
- 禁止手法を社内規程で明文化
- 台帳運用で継続改善を定着化
無料相談のご案内
制作やリニューアルで迷ったら、専門家に相談するのが近道です。ご要望やご予算、納期に合わせて最適な進め方をご提案します。はじめての方にもわかりやすい説明を心がけ、公開後の運用や集客まで一貫してサポート可能です。まずは気軽にお声がけください。
- 現状ヒアリングと課題の可視化
- 目的別の進め方と概算費用提示
- スケジュール案と体制のご提案
- 公開後サポートと改善方針の共有
- 他社見積との比較観点アドバイス
人気の関連資料のご案内
準備をスムーズに進められるよう、無料のチェックリストやテンプレートをご用意しています。制作前の要件定義シート、原稿作成の見出しテンプレ、SEOの基本チェックなど、すぐに実務で使える内容です。ダウンロードして社内共有し、共通認識づくりにお役立てください。
- 中小企業のウェブマーケティングロードマップ
- 今のホームページで大丈夫?ホームページ診断チェックリスト
- 採用×ホームページ|自社にあった人材を採用するためのコンテンツ戦略ガイド
- 基礎からわかるWebマーケティング入門ガイド
月額9800円〜|フルオーダーのサブスクホームページ
最近ではホームページのサブスクサービスも出てきており、高いデザイン性やクオリティのサイトがコストを押さえて運用することができるようになりました。
ウィルサポは月額9,800円からオリジナルのホームページをもてるサブスクサービスです。
SEO面もしっかりと対策した上で、お客様のビジネスの成長をサポートさせていただきます。LP制作や新規サイトはもちろん、サイトのリニューアルにも対応しております。
- 初期費用なしで月額9,800円から
- フルオーダーでデザイン作成
- サーバー、ドメイン費用無料
- サイトの保守費用無料
- 契約期間の縛りなし
- 集客サポートプランあり