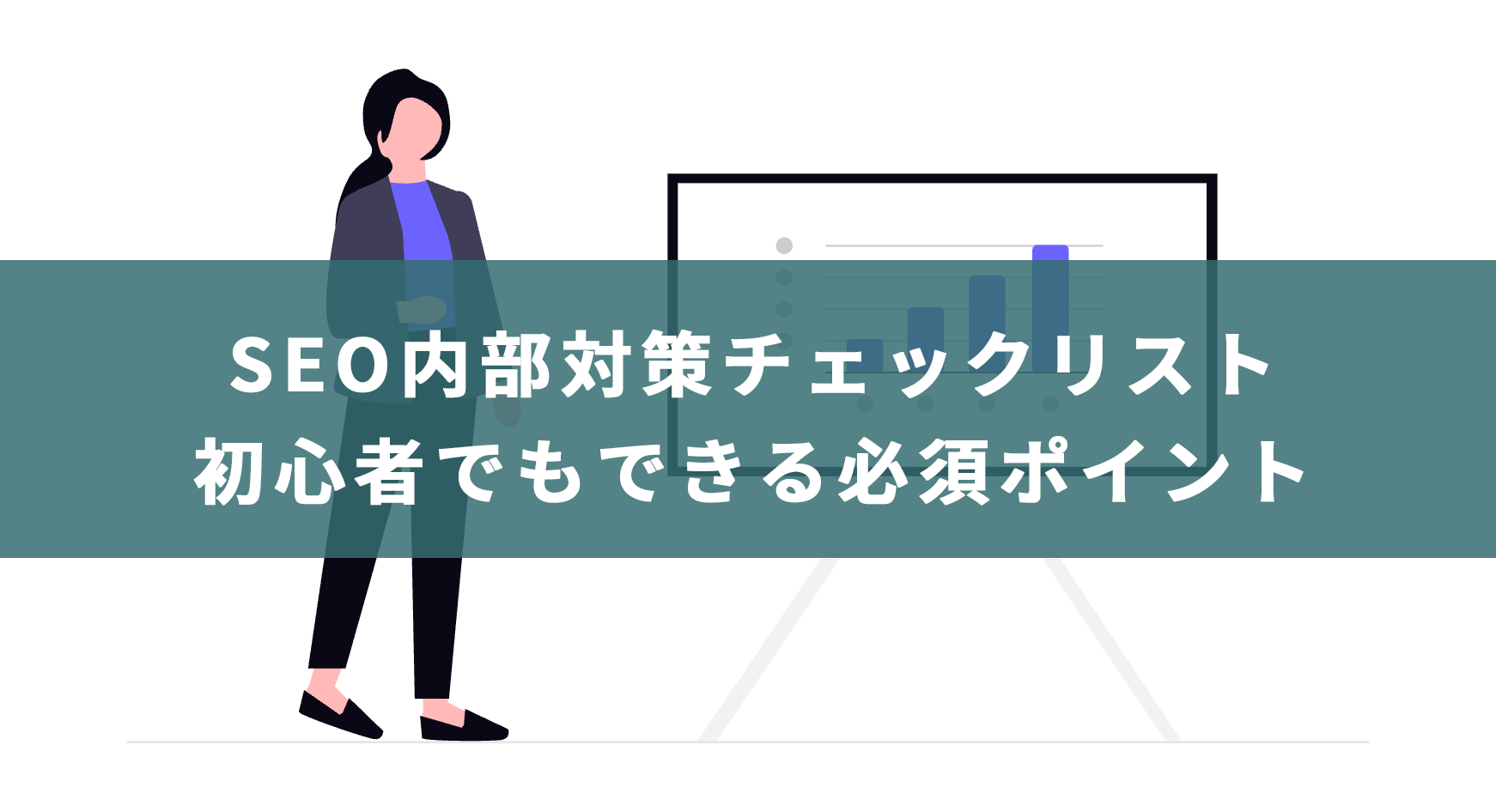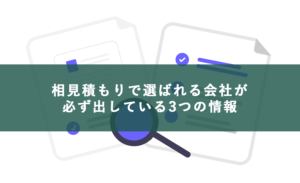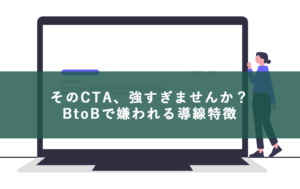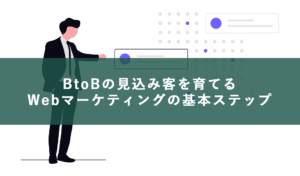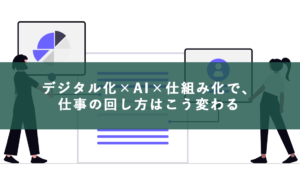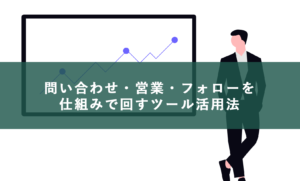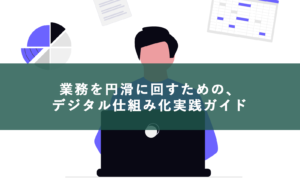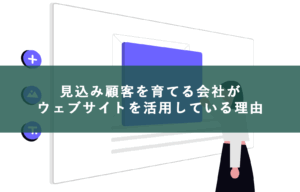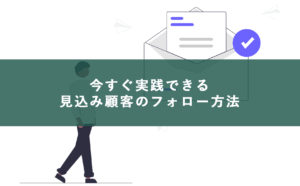はじめに
本記事は、検索結果で見つけてもらうための「内部対策」を、今日から実践できる手順で整理したガイドです。難しい専門用語は避け、サイトの土台づくり、ページごとの基本、技術面の確認、コンテンツ品質、計測と改善の流れまでを一気通貫で説明します。目的は「検索意図に合うページを、速く、見やすく、安心して読める状態」に整えることです。小さな改善の積み重ねで成果は安定します。チェックリストを使い、優先度と期限を決めて進めましょう。
こんな方におすすめの記事です
- 検索からの流入が増えず悩んでいる
- 何から着手すべきか順序で迷う
- 制作会社任せで全体像が不明
- 記事更新はしても反応が薄い
- サイトが遅く離脱率が高い
- スマホ表示が見づらいと感じる
- 構造化データに手を付けていない
- 測定と振り返りの習慣がない
- 古い記事の扱いに困っている
- 社内の運用体制が整っていない
この記事でわかること
- 内部対策の目的と基本思想
- 優先順位の付け方と判断軸
- サイト構造とURL設計の要点
- タイトルや見出しの作り方
- インデックス管理の基本設定
- 速度とモバイル最適化の勘所
- 画像や構造化の最適化手順
- 品質改善と重複対策の基準
- 必須ツールとKPIの選び方
- 月次運用のチェック体制
「中小企業のWebマーケティング|戦略ロードマップ」
無料ダウンロード資料配布中
【こんな方におすすめ】
- Webからの集客を増やしたいが、どの施策が効果的かわからない
- ホームページやSNSを活用しているが、問い合わせや売上につながらない
- 少ない予算・人員でも実践できるWebマーケティングの方法を知りたい
【この資料でわかること】
- 中小企業が成果を出すためのWebマーケティングの基本と成功ステップ
- 「アクセスが増えない」 「問い合わせが少ない」など、よくある課題の解決策
- 限られたリソースでも実践できる、最新のデジタルマーケティング手法
内部対策の基本
内部対策とは、サイト内の構造やページ内容、技術設定を検索意図と読者体験に合わせて整える取り組みの総称です。リンクを集める外部対策と違い、自社だけで進められ、積み上げが資産になります。大切なのは「検索する人が何を知りたいか」を出発点に、情報設計・本文・導線・速度・安全性を一貫させること。施策は小さく試し、効果が出る型を標準化して運用に落とし込むと、限られた工数でも成果を伸ばせます。
内部対策の目的と効果
内部対策の目的は、検索ユーザーの意図に対して「このページが最も役立つ」と検索エンジンと読者の両方に判断してもらうことです。効果は大きく三つに分かれます。第一に、適切なタイトルと見出し、本文構成で関連性が高まり、順位とクリック率の改善が期待できます。第二に、読み込み速度やモバイル最適化で離脱が減り、ページ滞在と回遊が伸びます。第三に、構造化データや正しいインデックス管理でページの評価が安定し、長期的に検索流入が積み上がります。これらは広告費の削減や営業効率にも直結するため、早めに着手して基盤を固める価値があります。
- 検索意図に合う答えを先に示す
- タイトルで価値と違いを明確化
- 見出しで論理構造を整理整頓
- 本文は結論→理由→具体例で書く
- 表示速度と体験品質を底上げする
- モバイルでの読みやすさを確保
- 構造化で内容の種類を機械可読化
- 正しくクロールとインデックス管理
優先順位の考え方
限られた時間で成果を出すには、影響度と実行難易度で優先順位を付けます。まずは全ページ共通で効く「タイトル最適化」「主要ページの速度改善」「モバイル表示の崩れ修正」「重要ページのインデックス管理」から着手すると効果が早い傾向です。次に、検索意図に合っていない古い記事の改稿や統合、内部リンクの張り直しなど、流入の土台を整えます。最後に、構造化データやテンプレ改修、画像フォーマット最適化などを段階的に広げ、標準運用に乗せます。月次で見直し、勝ち筋に集中しましょう。
- 影響度×難易度で案件を選別する
- 全体に効く共通改善から着手する
- 主要導線とCVページを最優先する
- 古い記事の改稿統合を前倒しする
- 内部リンクの網を再設計する
- 画像圧縮と遅延読込を標準化する
- 構造化データを型化して適用する
- 月次レビューで優先度を更新する
サイト構造とURL設計
サイトの骨組みが整理されているほど、検索エンジンもユーザーも内容を理解しやすくなります。情報の階層、カテゴリの意味づけ、パンくず、URLのルールを統一し、三クリック以内で主要情報に届く設計を目指します。初期に迷路化を避けると後工程の手戻りが減り、記事追加や改修が楽になります。
情報設計(IA)と階層化
情報設計では、ユーザーが探す道筋を先に決めます。トップ→カテゴリ→詳細という階層を基本に、パンくずで現在地を示し、ナビゲーションは用語を統一します。カテゴリは「検索意図」や「商材の分類」で分け、タグは横断テーマとして最小限にします。階層が深くなるほど到達率は下がるため、重要情報は浅い階層に置きます。サイトマップHTMLを用意し、関連ページには内部リンクで文脈上のつながりを持たせると、回遊が自然に増えます。設計は図に起こし、更新時も一貫性を保つことが重要です。
- 三クリック以内で主要情報へ誘導
- カテゴリの定義と粒度を統一する
- タグ乱立を避け用途を限定する
- パンくずで現在地を明示する
- HTMLサイトマップを設置する
- 関連性が高い内部リンクを張る
- 用語表を作り表記を統一する
- 構造図を更新時に必ず改訂する
URLポリシー
URLは英数字とハイフンで統一し、意味が推測できる短い構造にします。日本語URLや無意味なパラメータの多用は避け、wwwの有無や末尾スラッシュを統一します。重複URLは正規化タグや301リダイレクトで一本化し、検索エンジンが迷わない状態にします。カテゴリ移動などの変更は影響が大きいため、計画的に行い、旧URLから新URLへ恒久的リダイレクトを設定します。URL命名は今後の運用も踏まえてルール化し、担当者間で共有しましょう。
- 英数字とハイフンで可読性を確保
- wwwとスラッシュを方針で統一
- パラメータURLのインデックス制御
- canonicalで重複評価を一本化
- 301で恒久的にリダイレクト設定
- 短く意味のあるスラッグを採用
- URL変更は一覧管理で記録する
- 命名規則をドキュメント化する
ページ単位の基本要素
ページの評価は「タイトル→見出し→本文→内部リンク→メタ情報」の順に影響が大きい傾向です。検索意図に対する答えを冒頭で示し、読み進めるほど疑問が解消される構成にしましょう。各要素の書き方を型化すると、品質が安定し更新も楽になります。
タイトル(title)最適化
タイトルは検索結果で最初に見られる看板です。狙う検索意図と主要キーワードを自然に含め、ページの価値が一目で伝わる文にします。文字数は端末で切れにくい範囲を意識し、同サイト内で重複しないよう管理台帳を作るとミスが減ります。ブランド名を末尾に短く添えると信頼感が上がる場合もあります。クリックを煽りすぎる表現は離脱を招くため、具体的なメリットと対象読者を明確にする方が安定して成果につながります。
- 検索意図と主要語を自然に含める
- 切れにくい長さで要点を凝縮
- 重複防止の台帳で一元管理する
- 対象読者と利点を明確に示す
- 誇張より具体性を優先して書く
- ブランド名は短く末尾に付す
- ABテストで反応を検証する
- 更新日や数値で新鮮さを示す
見出し(h1〜h3)の設計
見出しは情報の目次です。h1はページの要点を一文で伝え、h2は大項目、h3は小項目として論理的に並べます。キーワードは不自然にならない範囲で含め、読者がスクロールだけで全体像をつかめる構成を意識します。見出しの語尾や文体は統一し、一覧ページや検索結果に表示されても意味が通る表現にします。見出しだけ読んでも結論が追えるように設計すると、滞在と満足度が上がります。
- h1は一つで要点を端的に示す
- h2→h3の階層を厳格に守る
- 見出しだけで全体像を掴ませる
- 文体と語尾をサイト内で統一
- 不自然でない範囲で語を含める
- 検索結果でも意味が通る表現
- 重複見出しを避け差別化する
- 更新時は目次も必ず修正する
メタディスクリプション
メタディスクリプションはクリックを後押しする説明文です。ページで得られる価値と対象読者、主な見出しの要点を要約し、行動を促す一文で締めます。同一サイト内での重複は避け、更新日や事例など新しさを感じる情報を入れると効果的です。自動生成に任せるよりも、重要ページは手書きで最適化し、検索結果での表示を確認して調整します。短すぎず長すぎず、読み切れる長さで整えましょう。
- 価値と対象読者を明確に示す
- 要点要約と行動喚起を含める
- サイト内の重複文面を避ける
- 更新日や事例で新鮮さを添える
- 重要ページは手書きで最適化
- 検索結果の表示を実機で確認
- 読み切れる長さに整える
- 定期的に効果を検証し改訂
本文と内部リンク
本文は結論を先に示し、理由と具体例、手順、注意点の順で展開すると読みやすくなります。内部リンクは文脈に沿って配置し、アンカーテキストはリンク先の内容が推測できる具体的な語にします。「こちら」や「詳細」だけの表記は避け、読者の次の疑問に答えるページへ自然につなげます。長文は見出しや箇条書きで区切り、図表がなくても理解できる文章に整えると、滞在と回遊が伸びます。CVへの導線も本文内で明確にしましょう。
- 結論→理由→具体例の順で構成
- 文脈に沿った内部リンクを配置
- アンカーは具体的な語を使用する
- 「こちら」表記のみを避ける
- 長文は小見出しで区切って整える
- 箇条書きで要点を簡潔に提示
- 次の疑問へ自然に誘導させる
- CV導線を本文内で明示する
技術面のチェック
技術的な不備は、内容が良くても評価や体験を損ねます。クロールとインデックスの制御、ページ速度、モバイル適合、セキュリティとエラーハンドリングを定期点検し、テンプレート側で恒常的に改善します。まずは重要ページから着手し、全体へ展開しましょう。
インデックス管理
検索エンジンに「どのページを評価してほしいか」を正しく伝える工程です。不要ページはnoindexで除外し、重複の恐れがあるページはcanonicalで正規URLを指定します。XMLサイトマップは自動更新に設定し、Search Consoleで送信状況とエラーを確認します。パラメータURLや検索結果ページのインデックスは基本的に避け、クロール予算を重要ページに集中させます。CMSの設定変更は配下全体に影響するため、テスト環境で事前検証する習慣を持ちましょう。
- 不要ページにnoindexを適用する
- canonicalで評価の重複を回避
- XMLサイトマップを自動更新
- Search Consoleで送信状況確認
- パラメータURLの露出を制御する
- サイト内検索結果は除外設定
- 重要URLを定期的にクロール確認
- 設定変更は検証環境で試験する
表示速度とCore Web Vitals
速度は離脱と順位の両方に影響します。画像の圧縮・適切なサイズ提供、遅延読み込み、不要スクリプトの削除や分割、キャッシュ設定、フォント最適化など、基本の積み上げが有効です。LCP・CLS・INPなど主要指標を把握し、テンプレート単位で改善を行うと全ページに効果が波及します。計測は実機とラボの両方で行い、影響の大きい上位テンプレから順に対処するのが効率的です。
- 画像を適正サイズと圧縮で提供
- 遅延読み込みで初期負荷を軽減
- 不要スクリプトを削除または分割
- キャッシュとCDNを正しく設定
- Webフォントの読み込みを最適化
- LCP/CLS/INPを定期的に監視
- 上位テンプレから順に改善着手
- 実機とラボ両面で計測確認する
モバイル対応
検索の大半はスマホからです。文字サイズ、行間、タップ領域、余白、折り返し、フォーム操作性を実機で確認し、片手操作でも迷わず読める設計にします。ビューポート設定は正しく、横スクロールや拡大前提のUIは避けます。画像や表は崩れないようレスポンシブ対応し、重要情報は折りたたみすぎないようにします。テストは複数端末で行い、実使用状況に合わせた改善を継続しましょう。
- 文字と行間を読みやすく調整
- タップ領域を最低基準で確保
- ビューポート設定を適切に指定
- 横スクロールの発生を防止する
- 表と画像をレスポンシブ化
- フォーム入力の負担を最小化
- 折りたたみ過多を避けて配置
- 複数端末で実機検証を実施
セキュリティとUX基盤
HTTPS常時化や混在コンテンツの解消は前提条件です。404ページは次の行動を案内し、301リダイレクトは適切に設定します。ポップアップや差し込み広告は閲覧を妨げない最小限に抑え、クッキーバナーや同意周りもわかりやすく設計します。安全で快適な体験は信頼の基礎となり、検索評価にも寄与します。定期的なプラグイン更新やバックアップで、トラブル時の復旧も想定しておきましょう。
- HTTPS常時化と証明書期限管理
- 混在コンテンツの警告を解消する
- 404に案内と検索窓を設置する
- 301で恒久的な遷移を定義する
- 侵入的な広告表示を控えめに
- 同意バナーを簡潔に設計する
- 更新とバックアップを定例化
- 障害時の復旧手順を文書化する
メディアとデータ
画像・動画は体験と速度に直結します。説明に必要な最小限で効果的に使い、代替テキストやファイル名で意味を補います。合わせて、構造化データでページ内容を機械可読にし、検索結果での理解を助けます。導入は型を作って継続適用がコツです。
画像・動画の最適化
画像は意味が伝わる最小サイズで用意し、ファイル名は内容が推測できる英字にします。alt属性は画像の役割を端的に記述し、装飾画像は空altで読み上げを妨げません。形式はWebPやAVIFを検討し、フォールバックも準備します。動画は圧縮とサムネイル最適化、遅延読み込みで初期表示を軽くします。キャプションや要約を添えると検索とアクセシビリティの両面で有利です。これらをテンプレ化し、追加時の手戻りを防ぎます。
- 内容が分かる英字ファイル名にする
- altで役割を簡潔に説明する
- 装飾画像は空altで読み上げ除外
- WebP/AVIFを優先的に採用する
- 遅延読み込みで初期負荷を軽減
- 動画は圧縮と適切な解像度に
- サムネイルを高速表示に最適化
- キャプションと要約を付与する
構造化データ(リッチリザルト)
構造化データは、ページの種類や要素を検索エンジンに伝える補助情報です。記事ならArticle、Q&AならFAQ、階層にはBreadcrumbなど、用途に合うスキーマを選択します。自動生成に頼りすぎると誤記や重複が起きるため、主要ページは検証ツールでエラーを確認します。内容とマークアップが一致していないと評価を落とすため、嘘や過度な最適化は避けます。実装はテンプレート化し、更新時も崩れない仕組みにしましょう。
- ページ種別に適切なスキーマを選ぶ
- 主要ページは検証ツールで確認
- 内容とマークアップの整合を担保
- 過剰な最適化や虚偽を避ける
- テンプレ化して再現性を高める
- 更新時の崩れを定期点検する
- パンくずで階層を明確に示す
- サイト全体で記法を統一する
コンテンツ運用と品質
評価されるのは「役に立つ具体情報」を持つページです。一次情報や実体験、事例、数字を示し、誰が書き、いつ更新したかを明らかにします。重複や薄い内容は統合・改稿・削除で整理し、サイト全体の品質を底上げします。運用体制も品質の一部です。
E-E-A-Tを意識した作り方
経験・専門性・権威性・信頼性を示すには、実務に基づく一次情報や検証結果、担当者の肩書や会社情報、問い合わせ先の明記が有効です。出典や根拠を適切に示し、更新日と変更点を記録します。医療や金融など重要分野でなくても、顔が見える情報は信頼を高めます。監修やレビュー体制があるなら紹介し、プロフィールページへつなぐ導線も用意しましょう。小さな積み重ねがサイト全体の評価につながります。
- 一次情報と検証結果を提示する
- 著者と会社情報を明確に記載
- 出典と根拠を適切に示す
- 更新日と変更点を記録する
- 監修やレビュー体制を紹介する
- 問い合わせ先を分かりやすく提示
- 事例で再現性と効果を示す
- プロフィール導線を整備する
重複・低品質コンテンツ対策
似た内容のページが多いと評価が分散します。検索意図が重なる記事は統合し、古い情報は最新化します。成果が乏しい薄いページは役割を再定義し、必要な情報を追記して改善、それでも不必要ならnoindexや削除を検討します。統合時はアクセスのあるURLを残し、301で評価を引き継ぎます。カテゴリー構成も見直して、重複を生みやすいテーマは整理しましょう。基準をドキュメント化し、定例で棚卸しすると安定します。
- 重複記事は統合して一本化する
- 古い情報は最新化して信頼維持
- 薄いページは追記改稿で強化する
- 不要なページはnoindexで整理
- 削除時は301で評価を引き継ぐ
- カテゴリ設計を見直し最適化
- 基準と手順を文書化して共有
- 定例棚卸しで継続的に管理する
計測と改善の進め方
計測は多すぎる指標で複雑にせず、検索流入とCVに直結する最小セットで運用します。Search Consoleとアナリティクスを連携し、順位・表示回数・クリック率・CVを月次で可視化。改善は仮説→実装→検証→学びの循環で回し、勝ちパターンをテンプレ化して全体に展開します。
必須ツール設定
Search Consoleではサイトマップ送信、インデックス状況、検索クエリの把握を行います。アナリティクスでは目標(資料DLや問い合わせ)を設定し、流入元ごとのCVを確認します。主要キーワードの順位やクリック率は週次で変動を見て、タイトルや見出しの改善につなげます。データの見方をチームで共有し、迷ったら「どの施策がCVに近づけたか」を基準に判断すると、投資の方向性がぶれません。
- サチコ連携とサイトマップ送信
- インデックス状況の警告を監視
- 目標とイベント計測を設定
- 流入別のCVを月次で確認
- 順位とCTRの変化を追跡
- 改善点を一枚に要約して共有
- 勝ち施策へ配分を素早く寄せる
- 撤退基準で無駄を抑制する
チェックリストと運用体制
改善は「誰が・いつまでに・何を・どう測るか」を明確にするほど進みます。月次の点検リストを作り、重要ページから順に実施。タスクは影響度と難易度で並べ替え、期限と担当を設定します。実装後は効果を記録し、成功手順をテンプレ化して再利用します。会議は指標の報告だけでなく、次の三手を合意する場にします。属人化を避け、引き継ぎ可能な運用ドキュメントを残しましょう。
- 月次点検リストで抜け漏れ防止
- 影響度と難易度で優先度を決定
- 担当者と期限を明確に設定
- 効果測定の方法を先に合意
- 成功手順をテンプレに落とす
- 会議で次の三手を決める
- 属人化を避け資料を整備する
- 変更履歴を記録して共有する
よくある失敗と回避策
内部対策は「やらないこと」を決めるのも重要です。キーワード詰め込みや過度な自動生成、技術改修だけで終わる改善は逆効果になり得ます。目的とKPIを先に決め、読者にとっての価値を基準に判断すると、無駄な作業を避けられます。小さく試し、学びを仕組みにしましょう。
やりがちなNGと対処
ありがちな失敗は、キーワードを不自然に詰める、似たページを量産して評価を分散させる、速度計測だけして改善に落ちない、構造化を目的化して内容と不一致になる、といった点です。対処はシンプルです。読者の疑問に先回りして答える構成を優先し、重複は統合、速度は画像とスクリプトの基本から、構造化は内容と一致する最小セットを正しく。計測はCVにつながる指標に絞り、月次で三つだけ改善を回すと継続できます。
- 不自然な語の多用を直ちに是正
- 重複記事は統合して評価集中
- 速度改善は画像とJSから着手
- 構造化は内容一致を厳守する
- 指標はCV直結の最小に限定
- 月次で改善三点に集中する
- 撤退基準を事前に決め遵守
- 学びをテンプレ化して共有
まとめ
内部対策は「検索意図に合う高品質なページを、速く安全に届ける」ための土台づくりです。サイト構造とURLの統一、タイトル・見出し・本文の型化、インデックスと速度の管理、画像と構造化の最適化、品質向上と計測運用――この順で小さく回せば成果は積み上がります。まずは重要ページを一枚選び、チェックリストで今月の三手を決めましょう。続けやすい仕組みに落とすことが、最短の近道です。
- 重要ページから順に改善を開始
- 統一ルールで構造と表記を整備
- タイトルと見出しを型で最適化
- インデックス管理を月次点検する
- 速度とモバイル体験を継続改善
- 画像と構造化をテンプレ化運用
- 重複統合と改稿で品質を底上げ
- 指標最小で検証と学びを継続
- 勝ち手順を標準化し横展開する
- 今月の三手を決めて実行する
無料相談のご案内
制作やリニューアルで迷ったら、専門家に相談するのが近道です。ご要望やご予算、納期に合わせて最適な進め方をご提案します。はじめての方にもわかりやすい説明を心がけ、公開後の運用や集客まで一貫してサポート可能です。まずは気軽にお声がけください。
- 現状ヒアリングと課題の可視化
- 目的別の進め方と概算費用提示
- スケジュール案と体制のご提案
- 公開後サポートと改善方針の共有
- 他社見積との比較観点アドバイス
人気の関連資料のご案内
準備をスムーズに進められるよう、無料のチェックリストやテンプレートをご用意しています。制作前の要件定義シート、原稿作成の見出しテンプレ、SEOの基本チェックなど、すぐに実務で使える内容です。ダウンロードして社内共有し、共通認識づくりにお役立てください。
- 中小企業のウェブマーケティングロードマップ
- 今のホームページで大丈夫?ホームページ診断チェックリスト
- 採用×ホームページ|自社にあった人材を採用するためのコンテンツ戦略ガイド
- 基礎からわかるWebマーケティング入門ガイド
月額9800円〜|フルオーダーのサブスクホームページ
最近ではホームページのサブスクサービスも出てきており、高いデザイン性やクオリティのサイトがコストを押さえて運用することができるようになりました。
ウィルサポは月額9,800円からオリジナルのホームページをもてるサブスクサービスです。
SEO面もしっかりと対策した上で、お客様のビジネスの成長をサポートさせていただきます。LP制作や新規サイトはもちろん、サイトのリニューアルにも対応しております。
- 初期費用なしで月額9,800円から
- フルオーダーでデザイン作成
- サーバー、ドメイン費用無料
- サイトの保守費用無料
- 契約期間の縛りなし
- 集客サポートプランあり